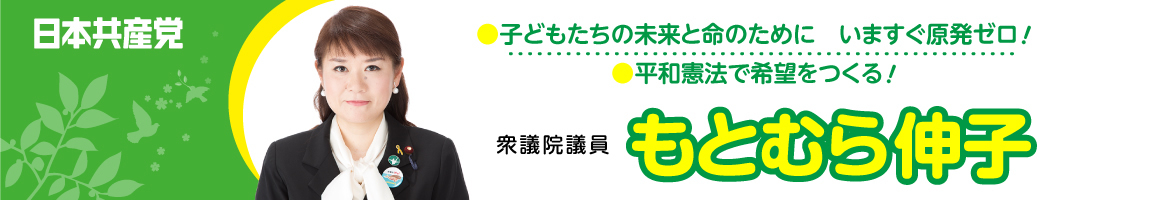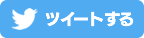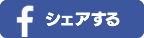マイナンバー法等改定案が17日の衆院地域・こども・デジタル特別委員会で、自民、公明、立民などの賛成多数で可決しました。日本共産党などは反対しました。
同案は国家資格の司法書士などの44事務や在留カード交付などの12事務で、マイナンバーの利用を可能とします。デジタル庁は国家資格などをマイナポータルと連携するシステムを開発し、昨年から一部資格で運用が始まっています。
同システムの利用が義務ではないと確認した上で、利用する場合は「有資格者の情報が蓄積されるのか」等の質問をしました。
質問の映像へのリンク
マイナンバー法改定で有資格情報取得か 差別や不公平助長のおそれ 2025.4.17
議事録
〇本村伸子
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
マイナンバー法案について質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、大前提ですけれども、あくまでマイナンバーカードの取得というのは任意であるということは変わりないかという点、また、事実上の強制がなされることがないようにするべきだというふうに考えます。
今、総務省は携帯電話不正利用防止法の施行規則の改定案、そして、警察庁は犯罪収益移転防止法の施行規則の改定案を公表し、携帯電話の契約と金融機関の口座開設時に必要な本人確認方法を改めるというふうに言っています。その改定案では、公的な本人確認書類に搭載したICを読み取る方法だけを残すというふうにしております。
ICチップが入っている本人確認のものといえば、マイナンバーカード以外に、運転免許証ですとかパスポート、在留カードがありますが、運転免許証などがない場合、実質的にマイナンバーカード強制になるのではないかということを懸念しております。
事実上の強制があってはならないというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○平国務大臣
マイナンバーカードは、法律にも規定されているように、国民の皆様の申請に基づき交付されるものです。そのため、国民の皆様に取得義務は課されておらず、取得を強制するものでもございません。
今般の犯収法施行規則等の改正は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等を踏まえ、自然人の非対面での本人確認方法をマイナンバーカードの
公的個人認証に原則一本化するものでございますが、マイナンバーカードを含むICチップつきの本人確認書類を保有しない者等への対応として、例えば住民票の写し等の書類の原本を利用する方法等、必要な補完措置を整備しているものと承知をしております。
○本村伸子
事実上の強制というふうに追い込まないように、是非、引き続きお願いをしたいというふうに、配慮をしていただきたいというふうに思っております。
一つ質問を飛ばしまして、三番で通告したところから質問させていただきたいというふうに思います。
資料の三を見ていただきますと、国家資格オンライン・デジタル化のシステム構成図ということで資料を出させていただきました。昨年八月から、図の右の方の国家資格等情報連携・活用システムの運用が開始をされております。
国家資格等に関し、このシステムの利用は義務なのか、そして、このシステムを利用する場合、有資格者の情報が蓄積されることになるのかという点、デジタル庁に伺いたいと思います。
○村上政府参考人
お答え申し上げます。
令和三年、五年に八十二の国家資格について行い、今回四十四の国家資格についてということでございますけれども、可能にする法的措置であって、義務づけるものではございません。デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムの利用を義務づける規定もございません。あくまでも、お願いをしながら、それぞれの御判断で御活用いただくものでございます。
なお、お尋ねをいただいたデータの方でございますが、国家資格等情報連携・活用システムを利用する場合には、各資格管理者がこれまでも保有してきた資格者に関する情報が、国家資格等情報連携・活用システムの方にそのまま連携して移るということになる。これを活用していただくに当たって、従来から持ってきた情報の範囲が広がるわけでも狭まるわけでもございません。
引き続き、また、一つのシステムにあるからといって他の資格の者はのぞくことができないようにするなど、資格管理者ごとにデータベースを論理的に分離し、厳格なアクセス制御を行うといったように、データの扱いについてはシステムの利用前後で変わらないように、しっかりとセキュリティーを担保しながら進めてまいりたいと思います。
○本村伸子
この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。
○平国務大臣
まずは、国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルのデータ連携は、国家資格のオンライン化、デジタル化として、具体的には、各種申請手続のデジタル化、オンライン化、その際の添付資料の省略や変更手続の省略、資格情報提示等のデジタル化などを実現するために行われるものでございます。
そのため、国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータル間のデータ連携としては、例えば、資格保有者が各種申請等を行う場合、資格保有者が自身の資格情報閲覧、提供等を行う場合において、氏名などの四情報、資格名、資格の登録番号、登録年月日などの情報がやり取りされることになります。
○本村伸子
また、民間事業者は、マイナポータルAPIの活用によって、本人同意が得られれば、個人に関する情報を取得することが可能となっております。
国家資格等保有者の情報が取得可能となり、看護師や保育士などの人手不足の分野で、有料職業紹介とかスポットワーク、こういう紹介に使われるのではないかというふうに考えますけれども、大臣、御所見を伺いたいと思います。
○平国務大臣
民間事業者がマイナポータルAPIの利用を申請した際には、デジタル庁が定めた規則に基づき、利用に関する社会通念上の相当性などの観点について、デジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります。社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないこととなります。
また、国家資格等保有者の情報は、現在、マイナポータルAPIで取得可能な情報には含まれておりません。
○本村伸子
現在はないんですけれども、今後つながっていくのではないかという懸念があるわけです。隙間バイト、スポットワークというのは、
失業時に失業給付を受け取ることができないですとか、あるいは、病気やけがによる休業時に健康保険の医療給付も受け取れないですとか、労災に遭ったときも不利な状況となってしまうということで、リスクが大変高い働き方であり、やはり規制が必要だというふうに考えております。
こども家庭庁の方では、保育士の配置基準に関しまして、スポットワーク、いわゆる隙間バイトにより採用された保育士を最低基準上の保育士の定数の一部に充てることは望ましくありませんというふうに通知を出しております。
子供さんやケアが必要な方々の命や安全、人権を守るために、ふさわしくない事態がなし崩し的に広がることがないよう、有料職業紹介が広がり現場が疲弊することがないよう、国家資格を持つケア労働者の有料職業紹介、スポットワーク、いわゆる隙間バイトに関するマイナポータルAPIの活用は認めるべきではないというふうに考えますけれども、大臣とこども家庭庁と厚生労働省に伺いたいというふうに思います。
○水田政府参考人
お答えいたします。
保育士資格は国家資格等情報連携・活用システムによるオンライン、デジタル化の対象となっておりますけれども、当該システムは、資格データを一元管理することで資格保有者と資格管理者の事務手続を簡略化し、利便性を向上させることを目的として、デジタル庁が主体となり、整備が進められているものと承知しております。
今後、更にどういった情報をどのような目的でマイナポータルAPIを通じて提供すべきかにつきましては、まずはこうした整備の状況も踏まえつつ、デジタル庁と連携して、必要に応じて検討してまいります。
なお、委員御指摘の、こども家庭庁より通知しましたスポットワークにより採用された保育士の取扱いについてでございますが、マイナポータルAPIの活用の有無にかかわらず適用されるものでございますが、引き続き保育所等が適正に運営されるよう取り組んでまいりたいと思います。
○森政府参考人
看護師等の国家資格保有者の関係についても、先ほどの保育士のこども家庭庁からの答弁と同様に、マイナポータルの活用については、各申請手続のオンライン化や資格情報の連携などの導入準備を現在進めているところでございます。
今後、更にどのような情報をどのような目的でマイナポータルAPIを通じて提供すべきかについては、まずはこの導入状況も踏まえつつ、デジタル庁と連携して対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○平国務大臣
スポットワークにより採用された保育士の取扱いに関するこども家庭庁からの通知については、適切に運用される必要があると考えております。
デジタル庁の立場から申し上げれば、アナログの制度で認められているものはデジタルでも認められる。なので、これはアナログの制度の問題だと思いますし、繰り返しになりますが、こども家庭庁の通知は尊重されるべきものというふうに考えております。
○本村伸子
こうした国家資格のケア労働者の方々の有料職業紹介は今でも物すごく深刻で、事業者の方が一人正規を紹介してもらったら、保育士でいうと二百万円払うとか百二十万円払うとか、そういう実態があるわけで、こうしたことが更に深刻になるような、特に、人間の使い捨てのようなスポットワークというようなことで、国家資格の方々が使い捨てされていくようなことがないように、子供たちの命や安全がしっかりと守られるようにということで手当てをしていただきたい、規制をしていただきたい、認めるべきではないということも強く求めたいというふうに思います。
次に、民間事業者等は、マイナポータルAPIの活用により本人同意が得られれば個人に関する情報を取得することが可能となっていますが、包括的同意や、同意の中身がよく分からないまま同意させられる形式的な同意、あるいは同意せざるを得ない状況下での同意、これはスマホなどを使っているとよくあることだというふうに思いますけれども、そういうような形で同意させるやり方を認めるべきではないというふうに考えますが、見解を伺いたいと思います。
そして、そうした問題のある形式的同意で個人に関する情報を取得し、ビッグデータやAI等を利用したプロファイリングを規制し、リクナビ事件のような選別や排除、不当な差別や不公平、こういうことを助長することを予防するべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○平国務大臣
所管外の質問も含まれておりますので、所管内の答弁をさせていただきたいと思います。
まず、一般論として申し上げれば、本人が自身の個人情報を民間事業者に提供する場合は、自らの意思により行われることが重要と考えております。
なお、マイナポータルAPIの利用申請に当たっては、デジタル庁が利用に関する社会通念上の相当性などの観点について、関係省庁とも協議の上、審査を行うこととなり、社会通念上、相当性が認められない場合は利用が認められないということになります。
○本村伸子
そこの基準が曖昧であるために、様々な情報が連携され、取得をされ、そしてプロファイリングされ、差別や排除につながっていくのではないかという懸念がございます。そうならないようにしていただきたいというふうに思います。
最後に、一番目の資料のところに今回の事務の拡大の点があるわけですけれども、在留カードの交付ですとか、国民保護法による救助の実施等が盛り込まれております。具体的にはどのような内容で、マイナンバーと在留資格に関する個人情報、国民保護法に関する個人情報はどのように管理され、ひもづけされるのか、どのような政策決定のプロセスで追加になったのかという点をデジタル庁に確認をさせていただきたいと思います。
○楠政府参考人
お答え申し上げます。
在留カードの交付等に関する事務では、外国人の在留カードに記載されている在留資格等に関する情報をマイナンバーとひもづけて管理し、これらの情報を必要とする入管庁以外の関係機関に提供することで、外国人が当該関係機関に申請等を行う際に在留カードの写しを提出するということが不要となります。
また、国民保護法による救援の実施等に関する事務では、避難住民の情報をマイナンバーとひもづけて管理することで、より確実かつ効率的な避難住民の情報の管理等が可能となり、一層迅速で的確な避難や救援の実施を図ることが可能となります。
いずれの事務についても、マイナンバーを含む個人情報の管理については、それぞれの行政機関において特定個人情報保護評価を実施し、漏えい防止等の安全管理措置を実施することが義務づけられております。
お尋ねの政策決定プロセスに関しましては、昨年六月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、各府省庁に対して、マイナンバー利用可能事務になっていない事務を対象に、マイナンバーの利用可能性の悉皆的な調査を行い、行政事務の効率化や国民の利便性の向上につながるものであり、各府省庁でマイナンバーの利用意向があるものについて利用可能事務に追加することとしたものでございます。
○本村伸子
デジタル庁の政策決定過程が不透明なところがある、説明の丁寧さが欠ける部分がございますので、そういうことを是正していただくことも強く求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
関連資料
マイナンバー法改定で有資格情報取得か 差別や不公平助長のおそれ