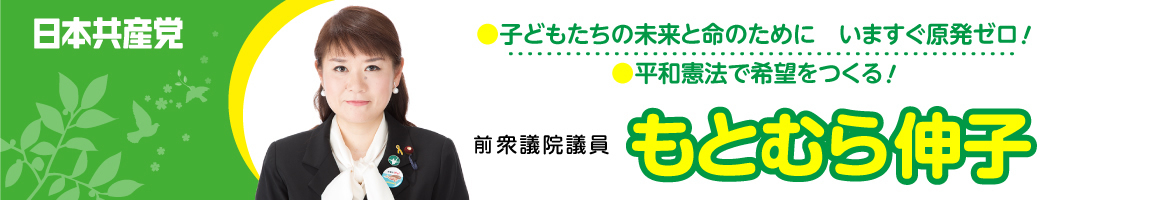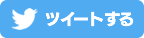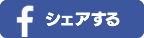質問の映像へのリンク
事件と無関係の情報押収も 刑事デジタル法案で参考人 2025.4.4
議事録
〇本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、電磁的記録提供命令に関しましてお伺いをしたいというふうに思います。
個人情報が不当に取得されてしまうのではないかという懸念がある中で、法務大臣とも質疑をさせていただく中で、提供を受ける情報は限定されるということで答弁をもらっているわけです。
そこで、まず、前提としてお伺いをしたいんですけれども、これまで裁判官の発する令状により、捜査、差押え、記録命令付差押えが行われてきたわけですけれども、被疑事件、被告事件と関係のないものが差し押さえられなかったかという点、これまでの事例について御存じの点を、全て、五人の皆さんにお伺いしたいと思います。
○吉開参考人
御質問ありがとうございます。
関係がないということの表現としまして、刑事訴訟法上は、被疑事実との関連性があるかどうかというところで判断をするところになります。
私も考えてみたんですけれども、例えば、ノートがあって、ノートの一ページに被疑事実に関連する情報がある。そのときに、ノートの一ページだけ破って押収するということはできないので、そのほかのページに関係ないことが仮に書いてあったとしても、一部に関係があれば、そのノートは差し押さえることになるのだろうというふうに思います。
ですので、関係がない情報を押さえたことがあるかという御質問に対しては、常に関連性は確認しているけれども、その関連性があるものを押収する過程において、付随的にと言えば表現が適切か分かりませんが、そういったものが押収されることもあるだろうというふうには思います。
○坂口参考人
現状として問題があるということは強く感じるところでございます。
例を挙げれば本当に切りがないというところだと思いますが、先月開催されたある院内集会のところで、国会議員さんの御発言の中で、過去の御経験として、御自身の親族が被疑事実の対象になった、御自身の幼少の頃の写真であるとか成績表も差し押さえられてしまって、持っていかれてしまって、それが乱暴な、段ボールに入れられて返ってきたという御発言をされた方がいらっしゃいました。
物理的に違うものということも含めて、現状に問題があるということは強く指摘せざるを得ないと思います。
○樋口参考人
大学で研究している身としましては、実例に直接接する機会がございませんので、お答えが難しい問題かと存じます。
○指宿参考人
先ほど御紹介した令和三年二月の最高裁決定の事案でも、七テラバイトの大量のデータが押収されています。これは専門用語で恐縮ですが、包括的差押えというふうに呼ばれています。
これは、現行刑事訴訟法上、適法とされています。ですので、端的なお答えとしては、日々行われている、現状それが問題である、これをどのように事後的にチェックするかという仕組みが我が国にないということだろうと思います。
先ほども御紹介しましたように、これを最高裁まで争った事例が僅かでしたので、このように具体的なケースを御紹介するしかありません。
特に、物理的な問題でしたら、今、坂口参考人から御紹介がありましたように、還付されますよね、押収された人に。自分のプライバシーに関わるものがどれだけ押収されたかということは分かるわけですが、電磁的記録について、情報主体には何の告知もありませんし、それが、新聞報道等で間接的に知ることができる程度ではないかというふうに思います。
以上です。
○池田参考人
お答え申し上げます。
私も具体的に実例を存じ上げているわけではありませんが、関連性を判断する際には、一つの被疑事実との間に関連性が認められると、およそ他の事実と関連性が失われるということではなくて、同時に複数の事実との間に関連性が認められることがあるということを踏まえて、無関係かどうかということを検討する必要があると思っております。
その上で、およそ意味を持たないということがあったかどうかということについては、つまびらかには存じませんので、これ以上お答えすることは差し控えたいと思います。
以上です。
○本村伸子
そうしますと、法制審の部会の中では、なかなかそうしたことは議論されてこなかったということでしょうか。お二人、法制審に出ておられました樋口参考人、池田参考人、是非お願いしたいと思います。
○樋口参考人
そうしたことというのは、従前の記録命令付差押えにおいて関係のないものが差し押さえられていたという事実ということでございましょうか。
専門が私は実体刑法でございまして、正確に議論の推移を把握できているか自信はございませんが、具体的な議論がなされたという記憶はございません。
○池田参考人
お答え申し上げます。
制度を論じるに当たりましては、やはり議論、プロセスとしては、現行の記録命令付差押えを出発点として、そこから媒体の移転を除いた部分という形で構想をされていきまして、その前提である記録命令付差押えが、およそ制度として地引き網的な情報の取得を内在しているというような認識に基づいていたわけではないということです。
そうでありますので、具体例としてこういうことがあるからという議論は、記憶の限りではなかったと承知しております。
○本村伸子
そういう点では、やはり国会の方でそれをしっかりと議論しなければいけないということもはっきりしたというふうに思います。
続きまして、この電磁的記録提供命令によって被疑事件、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報も取得されるのではないかという心配の声に対して、今回の法案の四百二十九条、四百三十条のところで準抗告ができるんだ、不服がある人は、裁判と処分の取消し、変更ができるというふうに法務省の方からは説明がされているわけです。
その被疑事件、被告事件と関係のない人が電磁的記録提供命令の令状が出されたことをどのように知ることができるのかという点を、法制審の部会に出られておられました樋口参考人、池田参考人、そして日弁連の坂口参考人に伺いたいというふうに思います。
○樋口参考人
法律制度として知る機会は与えられておらず、でも、事実上、何らかの契機で知るということはあり得るということにとどまるかと存じます。
○池田参考人
お答え申し上げます。
今、樋口参考人が申し上げたとおりでありまして、通知の制度というものは、現在のその物的証拠の収集、保全と同列に、利害関係者にあえて通知するという制度はなく、事実上、知る機会があれば不服申立てをし得るということにとどまっております。
○坂口参考人
今の参考人の方が御指摘のとおりでございまして、通知をする制度がない、そこがやはりきちっと、問題点として、日弁連としても指摘させていただいているところでございます。
○本村伸子
ですから、法務省が無理やり、法案の四百二十九条、四百三十条で準抗告ができるからということは、なかなか成り立ち難いというのが率直なところだというふうに明らかになったというふうに思います。
続きまして、通信傍受法と電磁的記録提供命令に、比較をいたしますと、その要件、手続、関係しない情報取得の防止の仕組みですとか消去の仕組みについて違いがあり、日弁連の皆様は大変それも危惧をされているというふうに思いますけれども、その違いについて、坂口参考人にお伺いをしたいと思います。
○坂口参考人
ありがとうございます。
通信傍受法との比較をすると、本当に様々指摘をされるところがあると思うんですけれども、まず、対象犯罪の限定がないというのは大きな違いだと思うんです。
通信傍受法は、薬物関連、銃器関連犯罪、集団密航の罪、組織的殺人等に限定されていますけれども、今回は対象犯罪の限定がないというところがありますね。
それから、先ほど御質問もいただきました不服申立ての機会を保障するための通知というのが、通信傍受法では、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知をしますけれども、今回の法案では、情報を取得された当事者に対して通知されないというところがございます。
それから、捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保措置として、通信傍受法では、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金というものが定められていますけれども、そういった制度的担保措置もないというところがございます。
そういった点もまさにございますので、今回の本法案については、きちっと個人のプライバシー、権利を守るための手当てが必要ということを日弁連は意見書等で申し上げております。
○本村伸子
ありがとうございます。
続きまして、指宿参考人にお伺いをしたいのですが、レジュメの中でも、時間がなくて御説明できなかったところがあるというふうに思います。それをお話しいただきたいのと、特に、欧州委員会から日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明さについて指摘をされているという点を是非教えていただければというふうに思っております。
○指宿参考人
お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。
お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。
捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側の電磁的通信、電気通信事業者等の透明性レポートの中で確認することができるだけです。
これは、私は転倒しているんじゃないかと思います。やはりデータを取得する側が、こういうふうなデータの取得をやっている、個人情報の収集をしているということを明確にするべきではないかなというふうに思います。これは、スライド十二ページ、十三、それから十四にございます。
この捜査関係事項照会では、非常にあらゆる個人情報が収集されているということが明らかになっています。
利用実態について、元警察幹部、元検察官の発言や企業アンケートによる実態調査、これは共同通信さんが行われて雑誌に公表されているもので、先生方も閲覧可能なものだと思います。
例えば、カードなどの利用履歴、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座、メールアドレス、家族情報、その他、店内防犯カメラ画像やレシート情報、こういうものが令状なく捜査関係事項照会で収集されているということを企業側は回答しており、大きな企業になると、この回答のための、照会を受けるための専門の部署が設置されて、日々、回答するための業務だけを扱っているというふうに聞いております。
これと同じような情報を、間接強制し、かつ事業者から収集するということが想定されるわけですけれども、この点についても大規模事業者からの意見聴取がされていないのはいかがかというふうに思います。
最後の御指摘がありました欧州委員会からの日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明性については、二〇一八年のオピ二オンというところでこれは明示されているところです。
これは、日本政府側の回答を受けて、十分性認定という結論に至っておりますけれども、日本政府側の回答は、捜査機関の扱う個人情報については国政調査権、公安委員会並びに総務省によって十分監督されており、違法に取得された場合には裁判所が証拠排除するという回答が公文書で送付されていますところ、国政調査権や公安委員会あるいは総務省によって、警察の個人情報収集が違法である、管理が不適切であると指摘された例を私は確認することができておりません。
また、違法収集証拠排除につきましても、先ほど井出議員の質問にもありましたように、重大な違法がないと証拠排除されませんので、通常の違法という表現が適切かどうか分かりませんけれども、重大に至らない違法の程度であれば排除されていないというのが現実で、数としてははるかにこちらの方が多いだろうというふうに推測している次第です。
以上です。
○西村委員長
本村さん、時間が来ていますので、お願いします。
○本村伸子
貴重な御意見、本当にありがとうございました。