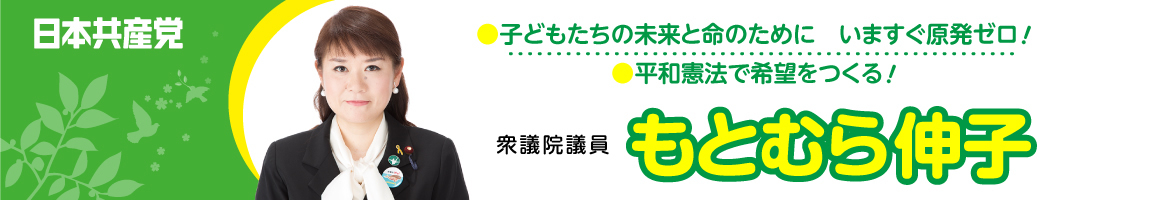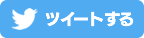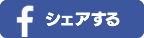民事裁判データベース法案が衆院法務委員会で自民党、立憲民主党、日本共産党などの賛成多数で可決しました。法案には、民事裁判の判決情報などを民間の指定非営利法人に委託し、仮名加工のうえ有償で提供する仕組みが盛り込まれています。
「なぜ国が直接運営せず、民間法人に委託するのか」「匿名加工前の情報が蓄積され、万が一流出すればデジタルタトゥーとなる。情報が他の業務に利用されてはならない」と裁判情報の徹底管理を求めました。
質問の映像へのリンク
民事データベース法案 民事裁判情報のプライバシー保護について 2025.4.25
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民事の判決の個人情報とプライバシー保護について質問をさせていただきたいと思います。
今回の法案、民事の判決の個人情報の加工、提供、管理、これをなぜ国の事業として行わず、民間の法人に委託をするのかという点、伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
これまでも何人かの委員の方々から同じような御指摘がありました。
そうした中で、私どもといたしましては、時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを、データベースの整備、運用においては図っていく必要があると考えております。
そうした中で、民事裁判情報の提供にこれまでも大きな役割を果たしてきた民間セクター、民間において相当の知見が蓄積をされ、さらには技術開発も進んでいる、そういった状況があろうかと思います。
そういった中で、私どもとしては、こうした民間の知見や技術をしっかりと活用していくこと、これが相当ではないかと考えたところでございますし、あるいはまた、国がもし仮にこうした整備、運用を行ったとした場合には、かなり所要の体制を整備するためのコストが必要であり、またあるいは、民間の方により蓄積をしているこうした知見や技術をどう獲得をするのかという問題も出てきます。
さらには、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理をするということへの懸念を招きかねないといった、そういったことも私どもとしては考慮したところでござ
います。
こうしたことに鑑みまして、さらには、有識者検討会の報告書も踏まえまして、基幹データベースの整備、運用については、国ではなく、法務大臣が監督をする民間の団体に行わせることとしたところでございます。
○本村伸子
これまでも民間の方が判決の写しを提供を受け、そして匿名加工、仮名の加工をして、有償で提供してきたというふうに思いますけれども、今までとは桁の違う判決の量を、二十五万件ということですけれども、膨大な個人情報、センシティブ情報が蓄積をされるということで、フェーズが違う段階に入ってくるということは、よく私たちは注意をしなければいけないというふうに思っております。
民事裁判の情報を、先ほどもおっしゃられたように、法務大臣が指定をする営利を目的としない法人が加工し、提供するという中身ですけれども、指定法人は様々な事業を行うということを想定しているのかという点、法務省に伺いたいと思います。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって、民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことその他を定めており、これらの要件については、申請をした法人が行う他の業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。
したがいまして、指定法人が他の業務を行うことそれ自体が制限されるものではございませんが、民事裁判情報の提供業務以外にどのような業務を行うかについては、指定の要件を備えるか否かを審査する際に考慮されることとなります。
○本村伸子
指定法人には仮名加工前の情報が蓄積をされるわけです。個人情報が一度流出をしてしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーとして残ってしまうこともございます。
加工前の情報がほかの業務に利用されるということはあってはならないというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
今委員がおっしゃったようなことは、決してあってはならないと私どもとしては考えております。
○本村伸子
民事裁判情報の加工、仮名加工情報の提供、そして管理という部分だけを非営利として考えるのか、ほかの事業のところは営利でいいのか、その点もお示しをいただきたいと思います。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。
本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うための費用を賄うことになると考えております。
○本村伸子
先ほど来議論がありますけれども、私も確認をしたいんですけれども、指定法人が仮名加工の民事裁判情報を提供する際の値段は幾らになるのかという点、お示しをいただきたいと思います。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
利用料金は、指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるように、一義的には指定法人において設定することとなりますが、不当に高額な金額とならないよう、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。
具体的には、指定法人による提供料金は、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
○本村伸子
次に、指定法人全体の事業が非営利であるべきだというふうに考えております。暴利を貪ったりですとか役員報酬が高かったり、本来、判決は、先ほど来御指摘がありますように公共財ですから、その利益は国民、住民の皆様にお返し
をしなければいけないということになります。ですから、一部の人が一般の方の収入よりもかなり高い収入を得るということは、納得は全くされないというふうに思います。
指定法人全体の事業が非営利であるべきというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいと思います。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、非営利の法人を指定法人として指定することとしておりますので、指定法人が行う他の業務についてもまた非営利法人として行う業務ということになります。
もっとも、先ほどお答えしたとおり、およそ指定法人がその事業により収益を上げることが許されないものではないと考えているところでございます。
○本村伸子
その利益は国民、住民の皆様にお返しできるようにということでしていただきたいというふうに思います。
民事訴訟法の第九十二条第一項には、訴訟記録の公開の原則を、例外的に認める規定で、当事者の申立てによって訴訟記録の一部を閲覧制限することができると定めております。しかし、事件に何の利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を一切のマスキングがされないまま閲覧をできる状況にあるということが報告をされております。
この法案は、この現行法の閲覧制限の場合は提供しないというふうにありますけれども、しかし、今のままでは不十分だというお声がございまして、この法案で本当にプライバシー情報が守られるのかという点も大変懸念をしておりますけれども、その点、いかがでしょうか。
○鈴木国務大臣
まさにこの訴訟関係者のプライバシー、この権利利益は極めて大事だと思っております。
そういったことの配慮ということで、先ほど委員からも御指摘がありましたけれども、まず、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定あるいは閲覧等制限決定の対象となった情報については、取得をまずしないということがございます。
そのことに加えまして、利用者への提供に当たっては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、特定の個人を識別することができる情報等に仮名処理を行う、あるいは、申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行う等の仕組み、これを私どもとしては設けているところであります。
こうした仕組みの下で、訴訟関係者のプライバシー、こうした権利利益の保護、これは十分に図られるものと私どもとしては考えておりまして、法務省令を通じて適切な仮名処理の基準を定める、あるいは、先ほど質疑の中でもどなたかとの審議でございましたけれども、この制度の適切な周知徹底、これは極めて重要だと思っておりますので、訴訟関係者の方々ができる限り負担なく必要な申出をしていくことができるよう、我々としては努めていきたいと考えております。
○本村伸子
それで、これから仮名加工されるということですけれども、個人情報については、本人と分からないように提供することが必要だというふうに考えます。
以前、デジタル関連法案の質疑のときに、行政が保有している個人情報の利活用の匿名加工の部分で、名前は消すけれども、郵便番号ですとか職業ですとか家族構成ですとか年齢とか性別、これを百十八万人分、銀行に提供したという事例がございまして、郵便番号と職業、家族構成、これでもうかなり、例えば弁護士ですとか医師とか、そういうところになれば、とりわけもう個人は特定されてしまうということになってしまいます。
そうしたことがないようにするべきだというふうに思いますけれども、法務省に伺いたいと思います。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などについて仮名処理の対象とすることを想定しております。
さらに、基準に沿って仮名処理を実施しても、
報道された情報等と組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしておりまして、以上の措置を通じて、訴訟関係者の特定を避け、その権利利益に配慮することとしております。
○本村伸子
本人と分からないように提供していただくということが肝要だというふうに思います。
特に性暴力被害当事者の方やDV、虐待の被害当事者の方、あるいは暴力団の関係で被害を受けた方々など、仮名加工したとしても非公開を望む原告の方々はいらっしゃるというふうに思います。そういう原告の方々の意思はどのように反映されるのか。必ず意思は確認されるのか。閲覧制限の制度ですとか、あるいは追加で仮名加工できるというふうになっておりますけれども、そのことの制度を知らなかったら利用することができないわけですから、最高裁の方には必ずそうした制度を教示をするということを求めたいというふうに思いますけれども、これは最高裁と法務大臣にお伺いをしたいと思います。
○西村委員長
最高裁福田民事局長、時間が来ますので、答弁、簡潔にお願いします。
○福田最高裁判所長官代理者
お答えいたします。
まず、現在においても、性暴力被害当事者など、訴訟記録に私生活についての重大な秘密が記載され、それが明らかになることにより社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある方から、そのような私生活上の秘密について第三者に知られたくないとの相談があった場合には、裁判所において閲覧等制限の制度について教示をし、その申立てを促すなどしているものと承知をしております。こうした実務の取扱いは、本法案の成立後においても続けられるものと認識しております。
また、本法案成立後につきましては、民事裁判情報の非公開を望む当事者に対し、委員御指摘の追加の仮名加工処理制度の利用も含め、手続が適切に周知されるように検討してまいります。
○鈴木国務大臣
今の点でありますが、当然のことながら、性暴力被害者、当事者などの方々については、そのプライバシー、権利利益に十分に配慮する、これは当然のことでありますし、極めて大事なことだと思っております。
その上でありますけれども、こうした民事裁判情報、まず公開の法廷における裁判の結果ということでありまして、今これは裁判所の方からも御答弁があったかと思いますが、そもそもが閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものであります。その上で、こうした制限がかかるかどうかについて今御答弁があったところだと思います。
加えて、こうした同意を全てさせるのかといったことでありますけれども、それはやはりなかなか基幹データベースとして成り立たなくなる、そういった指摘も様々あったことから、そうしたことはいたしませんが、しかし、この制度でも設けられました追加的な仮名処理などの仕組み、さらにはその適切な周知、私どもとしては、それをしっかり図っていくことで、訴訟関係者の権利利益、適切に配慮していきたいと思っております。
○西村委員長
本村さん、終わってください。
○本村伸子
裁判を受ける権利を保障するためにも個人情報の保護というのは必要だというふうに思いますので、是非その点を強く求めて質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。