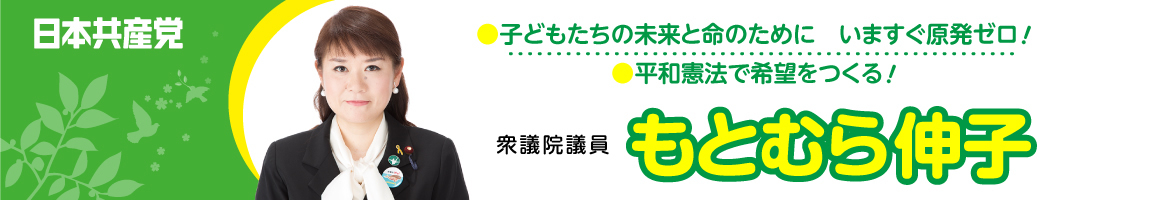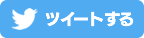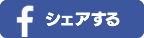衆院法務委員会で、刑事デジタル法案は、捜査機関による個人情報収集に歯止めがなく、人権やプライバシーの侵害を引き起こす危険性が通信傍受法(盗聴法)以上に高いと警告しました。
質問の映像へのリンク
刑事デジタル法案 人権侵害の情報収集 「盗聴法より危険」 2025.4.9
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
犯罪と関係のない個人の情報が収集、蓄積、利用される危険性についてお伺いをしたいと思います。
通告の三番からまずお伺いをしたいというふうに思っております。
電磁的記録提供命令によって、被疑、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報が取得されるのではないかという心配の声に対して、法務省は、一応法案で、四百二十九条、四百三十条で、電磁的記録提供命令の令状に不服がある者は裁判所にその処分の取消しと変更を請求することができるんだというふうに、準抗告ができるんだというふうに御説明を私は受けました。
しかし、クラウド事業者に命令が出た場合、被疑者、被告人も含まれるというふうに思いますけれども、事件と関係のない人がどういうふうに、電磁的記録提供命令の令状が出されたこと、自分の情報が取得されるのではないかということを確認したらいいのかという点、大臣にお伺いしたいというふうに思いますし、本当は準抗告はほとんど使えないのではないかというふうに思いますが、そのことをお認めいただきたいと思います。
○鈴木国務大臣
この法律案におきまして、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録に記録された情報の主体に対する処分の通知、これは捜査機関に義務づけることとはしておりません。
そういった中で、実質的に見ても、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、電磁的記録提供命令あるいは差押え等がなされた事実の通知等をしなければならないとした場合には、先ほど来、いろいろ御答弁申し上げています。
けれども、やはり捜査記録の活動内容が捜査対象者に広く知られることとなり得るということで、捜査の密行性を確保できなくなるといった点、あるいは、罪証隠滅行為あるいは被疑者逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということ、さらには、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する人物を全て特定した上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、そのようなことは現実的に困難である上に、捜査の迅速性も著しく損なわれることとなる等の問題があると我々としては考えております。
そういった中にあって、この法律案においてそうした通知等の仕組みを設けないということとしておるのは、そういった背景ということでございます。
○本村伸子
多分、聞かれたことと答えていることが違うというふうに思うんですけれども。
準抗告は全く犯罪と関係ない人はほとんど使えませんねということをお認めいただきたいと思います。
○鈴木国務大臣
そういったことで申し上げれば、例えば、情報通信事業者等からそうした情報主体に対して、そうした命令が発出されたということ、これが確認できない場合にはそういったこととなりますけれども、そこは必ずしも一〇〇%そうなるかということであれば、一〇〇%そうなるということではないと承知をしております。
○本村伸子
偶然知ることができたら、自分の情報が収集されていることが分かる、その段階で不服申立てができるレベルでいいのかという問題なんです。それは本当に偶然知って不服申立てができるということになりますので、全く不十分だというふうに思います。
この不服申立ての機会を保障するための通知について、通信傍受法ではどうなっているのか、お示しをいただきたいと思います。
〇森本政府参考人
通信傍受法の第三十条一項においては、検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成したこと等を通知しなければならないこととされております。
○本村伸子
盗聴法と呼ばれる通信傍受法では通知をされるわけです。なぜ今回の記録提供命令ではできないのかという問題があります。
盗聴法に関しましては、通信傍受法ですけれども、憲法二十一条二項の通信の秘密、十三条に基づくプライバシー権の権利を侵害するということで、私たちとしては廃止を求めているわけですけれども、それでも、皆さんの心配もあってだというふうに思いますけれども、皆さんの声が少し規制を強めたというふうに思いますけれども、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知がされます。
この通信傍受法の対象犯罪と電磁的記録提供命令の対象犯罪、それぞれお示しをいただきたいと思います。
○森本政府参考人
まず、通信傍受法の対象犯罪でございますが、いわゆる薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人が別表の一に定められているほか、殺傷犯関係犯罪、逮捕監禁・略取誘拐関係犯罪、窃盗・強盗関係犯罪、詐欺・恐喝関係犯罪、児童ポルノ関係犯罪が別表二に掲げられております。このうち、強盗、詐欺、恐喝につきましては、現在、ちょっと細かい言い方になりますが、一項犯罪というものだけが対象とされておりますが、今回の改正で二項犯罪を追加していただくことをお願いしているというのが対象犯罪の範囲でございます。
他方で、電磁的記録提供命令につきましては、対象犯罪を規定することとはしておりません。
○本村伸子
今回の電磁的記録提供命令に関しましては、犯罪の限定もないわけです。
今日は資料をお示しをしておりまして、先ほどの通知の点は、上から五番目の表を見ていただきますと、電磁的記録提供命令と通信傍受のところで違いがよく分かっていただけるというふうに思いますし、「要件」というところで、対象犯罪、今回は限定がないのだというところも含めて見ていただけるというふうに思います。
通信傍受法では、例えば凶悪な犯罪でも不服申立ての機会を保障する通知はあるのに、記録命令つきの差押え、今の現行法でも、そして電磁的記録提供命令でもないのは不当であるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
今御指摘ありました通信傍受法によります通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであります。よ
って、これは継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密、これを制約する性質の処分であります。
一方で、電磁的記録提供命令でありますけれども、こちらの通信傍受とは異なって、これは繰り返し答弁もさせていただいていますけれども、既に存在をしている電磁的記録の記録や提供を命ずるというものにとどまるわけであります。そういった観点からいえば、先ほど通信傍受法の下での通信傍受において申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、その二つを同列に論じる、比較するということではないと考えております。
実質的にも被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、記録命令付差押えあるいは電磁的記録提供命令がなされた事実を通知しなければならないとすることについては、先ほど来申し上げている様々な問題があると考えておりまして、相当ではないと考えているのは先ほど御答弁申し上げたとおりであります。
そうしたことから考えれば、記録命令付差押えあるいは電磁的記録提供命令について、そこで通信傍受法と異なるという御指摘だと思いますけれども、被処分者以外の者に対する通知の仕組みがないということ、私どもとしては不当であるとは考えてはおりません。
○本村伸子
通信傍受法はリアルタイムであるということも一方で法務省からも言われました。しかし、二〇二四年中の通信傍受の実施状況国会報告概要というものを見させていただきましたけれども、二〇二四年中の傍受方法でいいますと、一時的保存をされたもので盗聴しているというのがほとんどなんですよね。ほとんどのケースが一時的保存をして、それで聞いているという点で、リアルタイムなのか保存されたものなのかという点では全く理由にならないというふうに思いますし、継続性ということであれば、何月から何月までというふうに限定をしない場合も継続性はあるというふうに思いますけれども、その点、いかがでしょうか、大臣。
○鈴木国務大臣
リアルタイムということではなく、まさに先ほど申し上げましたけれども、通信傍受の方は当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであるというもので、これは継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約をする性質の処分ということで、そうした趣旨から今回の電磁的記録提供命令とは異なるという趣旨で御答弁申し上げたところであります。
○本村伸子
済みません、電磁的記録提供命令は、じゃ、どこに同意を得るんですか。
○鈴木国務大臣
電磁的記録提供命令は、先ほど申し上げましたように、既に存在をしている記録、ここの電磁的記録の記録や提供を命ずるにとどまっているところであります。これはそうした供述というものを強いるというものではないというのは答弁を申し上げているとおりでありまして、そうした趣旨から、通信傍受法に基づく通信傍受と電磁的記録提供命令、これはそうした同列での比較にはなじまないと考えております。
○本村伸子
全く理由になっていないというふうに思うんですね。
通信傍受法については犯罪と関係のない情報の取得を防止するための手続はどうなっているのか、そして電磁的記録提供命令ではどうなっているのかという点をお示しをいただきたいと思います。
○森本政府参考人
通信傍受法におきましては、別表に掲げる対象犯罪について、同法が定める厳格な要件を満たす場合に、裁判官が発する傍受令状により、傍受すべき通信が行われる蓋然性のある特定の通信手段に限り、通信を傍受することができるものとされております。
また、同法におきましては、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、いわゆるスポット傍受として、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するのに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができることとされております。
なお、先ほど委員から、一時保存が多くてリアルがないという話がありましたが、一時保存というのも、過去にあるものではなくて、令状請求した段階ではないものについて、現在から将来に向けての通信を傍受した、その記録をもらってくるというものでございますので、やはり同列には論じられないものというふうに考えております。
○本村伸子
一時保存したものだけもあるんですけれども、その場合はどうなるんでしょうか。
○森本政府参考人
一時保存のものが多いのは、委員御指摘のとおりでございます。
一時保存のものというのも、通信傍受は現在から将来に向けての通信を傍受しますので、令状請求して、こういう要件で、犯罪関連通信が行われるのが相当だといって令状が出ますと、ここから先の会話について傍受して一時保存したものが警察に事後にやってくる、記録として。そういう仕組みになっているものというふうに承知しております。
○本村伸子
じゃ、将来か過去かという点で違うということだとは思いますけれども、その内容については、どちらが重要なのかというのはその内容によるわけで、通信傍受法であるのか、電磁的記録提供命令であるのかという点では違いがないというふうに思います。
そして、今言われた、答弁されましたように、通信傍受法の中では限定があるけれども、しかし、電磁的記録提供命令の方では、犯罪と無関係な情報の取得を防止するための手続がないということも答弁をしていただきました。
そして、次に、通信傍受法では犯罪と無関係な情報を消去する手続はどうなっているのかという点、そして、電磁的記録提供命令ではどうなっているのかという点、お示しをいただきたいと思います。
○森本政府参考人
お答えいたします。
通信傍受法二十九条におきましては、検察官又は司法警察員は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受をした通信を記録した記録媒体等から、傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して作成するものとされております。
電磁的記録提供命令におきまして、電磁的記録提供命令に基づいて提供を受けた記録の消去に関する規定はございません。
○本村伸子
この表の四番目のところですけれども、通信傍受では、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らないというふうにありますけれども、今回の電磁的記録提供命令では、そういった、ずっと蓄積をされるという問題があります。
そしてもう一つ、通信傍受法では違法な手続で取得をされた情報は消去をされるのか、電磁的記録提供命令では消去をされるのか、お伺いをしたいと思います。
○森本政府参考人
お答えいたします。
通信傍受法第三十三条第三項におきましては、裁判所は、傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらないときなどには、検察官等に対し、その保管する傍受記録等のうち当該傍受の処分に係る通信等の消去を命じなければならないこととされております。
それに対しまして、電磁的記録提供命令につきましては、先ほど申し上げましたとおり、消去に関する規定はございません。
○本村伸子
違法に取得をされた情報を、通信傍受法では、裁判所は消去を命じなければならないとあるのに、電磁的記録提供命令はそれもないわけです。
また、通信傍受法では捜査機関の濫用を防止するための制度的担保として罰則がありますけれども、その罰則をお示しいただきたいと思います。また、電磁的記録提供命令では、捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保、どうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
○森本政府参考人
通信傍受法におきましては、捜査等の権限を有する公務員がその捜査等の職務に関し、電気通信事業法等に規定する通信の秘密を侵す行為の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされております。
これは、通信傍受が現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであり、継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であることを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとしたものと考えられます。
これに対して、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受と異なり既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことなどを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとはしておりません。
○本村伸子
捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保が電磁的記録提供命令ではないわけです。その点も、盗聴法よりも危険性があるわけです。
私たちは、盗聴法と呼ばれる通信傍受法、これも問題だと思いますけれども、その問題ある通信傍受法でさえ、被疑者、被告人の個人情報を慎重に扱う姿勢があるにもかかわらず、あるいは第三者の方々の個人情報を扱う慎重さがあるにもかかわらず、電磁的記録提供命令は、何の罪もない人の情報さえ捜査機関が容易に取得をでき、そしてプロファイリング、使われたり、人権侵害、プライバシー侵害を引き起こされる危険性が高いものとなっております。そういう認識を、法務大臣、持つべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○鈴木国務大臣
先ほど来申し上げておりますけれども、通信傍受法による通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うということで、これはまさに継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約するものであります。
その一方で、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受とは異なって、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまっておりまして、これは現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、そうした継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないわけであります。
そうした中で、それを同じ次元での比較ということとは、我々としては、認識は、そういう認識ではおりませんので、その点は御理解をいただきたいと思います。
○本村伸子
個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。