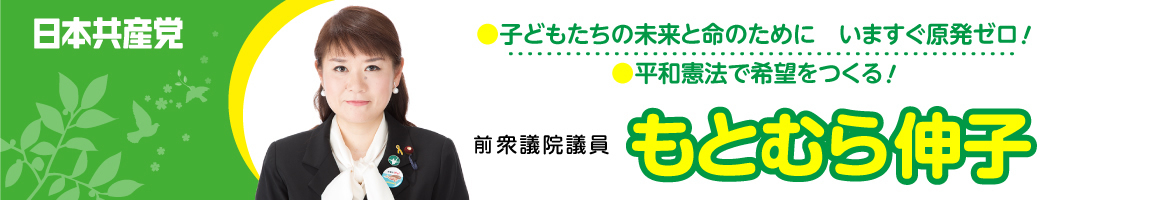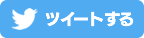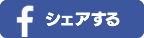衆院法務委員会で、現行法の下でも捜査機関が犯罪と関係ない違法な個人情報の収集を行っており、刑事デジタル法案で人権侵害の危険性がより高まるとして、捜査機関による情報収集や保存、利用の乱用を防止する法的措置を求めました。
質問の映像へのリンク
https://youtu.be/0nX6R9LfLxk?si=ADFhOqHcv6WaVAu_
議事録
〇本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日は、捜査機関による個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用防止に関して質問をさせていただきたいと思います。
まず、大前提で伺います。憲法十三条についてです。
個人の情報をみだりに第三者に開示又は公表、提供されない自由のみならず、その前段階とも言える個人情報の収集及び保有についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないと言うべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた憲法十三条により保障されていると解すべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
今、本村先生おっしゃいました憲法十三条でありますけれども、これは、全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると規定をされているところであります。
これは、最高裁の判例等々におきまして、この憲法第十三条につきましては、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解されると判示をされているところであります。
ただ、もっとも、そうした個人の私生活上の自由というものを、もちろんこれは絶対的に無制約ということではなくて、例えば、犯罪捜査といった公共の福祉の要請に基づいて、憲法及び刑事訴訟法の規定等の下で一定の制約を受ける場合というものはこれはあるのではないかと我々としては認識をしております。
○本村伸子
捜査機関が犯罪に関して個人の情報を収集することはあり得るというふうに思うんですけれども、それでも、濫用がないように、例えば全く関係のない情報を収集するなどがないように、本来は法的な根拠をもって律すべきだというふうに考えます。
先日、参考人質疑をお伺いをいたしましたけれども、現行法上の捜査機関は、令状を取っていますけれども、犯罪と関係のない個人情報を取得しているということがはっきりといたしました。
その現行法上の問題をそのままに引き継ぐ形で、電磁的記録提供命令、そして、命令に従わない場合の罰則、捜査機関に提供したことを漏らしてはいけないという秘密保持命令、そして、その秘密保持命令に違反した場合の罰則が法案で盛り込まれております。プライバシーの侵害、そしてプロファイリングの規制もない中で、更に個人情報の不当な収集と蓄積、利用ということにつながるのではないかという懸念があるわけです。
ある参考人の方は、やはり現行法が問題なのだということを実際に参考人としておっしゃられた方もおられますし、平場で、こういう場でそういうふうに私におっしゃってくださった方もおられます。
ですから、現行法の問題もしっかりとこの場で議論しなければいけないということで、今日は、その観点から質問をさせていただきたいというふうに思っております。
以前も取り上げさせていただきました大垣警察の市民監視事件、名古屋高等裁判所の判決の中で、警察が違法行為を行っていたことが断罪されました。何の罪もない、むしろ、市民活動をして、より透明性のある、そして、公共の場での実質的な議論が可能になるような、関心が高まるような、そういう社会的に望ましい活動をされていたということが判決の中でも評価されている、そういうお一人お一人の個人情報を取得、保有、利用していたことが違法とされたわけです。
これまでの国会答弁では、当時の国家公安委員会委員長が、通常行っている警察業務の一環であるというふうに強弁をしていたわけですけれども、それが違法とされました。
違法とされた、通常行っている警察業務の認識が正されているのか、通知や通達などで全国の警察職員にその認識が正されるような広報をしているのかという趣旨で四月一日に私が質問をしたところ、警察庁長官官房審議官からこのような答弁がありました。結果といたしましては、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきまして、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところでございます。いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでございまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を執行するよう、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えておりますというふうな答弁が返ってまいりました。
でも、私が問うたことに関して、正面から答えていただけなかったというふうに思っております。通常行っている警察業務が違法とされた、そういうことから、全国の警察職員の認識を正すために、個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用を防ぐルール、これを通知や通達などで知らせる必要があるというふうに思います。今までどのようなことを警察庁としてはやってきたのかという点、お示しをいただきたいと思います。
○石川政府参考人
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、昨年九月の名古屋高裁の判決を受けまして、警察庁から各都道府県警察に対しまして、昨年十月三日に、適切な情収集活動についてとの通達を発出しております。
この通達におきまして、警察法第二条に基づく情報収集活動における目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則の遵守でありますとか、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示をしているところでございます。
また、これに加えまして、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議でありますとか、あるいは、警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対しまして、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いについて重ねて指導しているところでございまして、引き続き、様々な機会を捉えまして、都道府県警察を指導して
まいりたいというふうに考えております。
○本村伸子
そうしたことをやっていただいているんですけれども、法文上にはしっかりとした明記がないという中で、濫用を防ぐことができていないわけです。
この大垣警察の市民監視事件に関しまして、判決でとても大事な点があるので、これも紹介をしていただきたいと思います。憲法上の人格権としてのプライバシーの部分であります。
判決の四十六ページ二十六行目の「公権力が、本人の知らないまま、」から、四十七ページの十九行目、「弊害も生じ得るのである。」というところまで御紹介をいただければと思います。
○福田最高裁判所長官代理者
委員御指摘の部分、裁判所ホームページ掲載の判決文の四十六ページ二十六行目から、四十七ページ十九行目までを読み上げます。
公権力が、本人の知らないまま、特定の個人 に関する個人情報を、その要保護性の高低、推 定的同意の有無、収集方法の強制処分性又は任 意手段性の如何、正確性の有無や程度等にかか わらず、多数収集してこれらを集積し、分析し、 保有するなどすれば、当該個人の実際の人間像 (人物像)とは異なる人間像がその中で形成さ れ、これが独り歩きして、誤った個人情報に基 づく措置等を行ってしまう可能性がある。また、 保有する情報が不十分なもの(重要な意味を持 つ関連情報が欠落する場合などもあり得る。) である場合は、本来であれば考慮すべき情報を 考慮せずに意思決定し、それに基づく措置等を 行ってしまう危険性も生じ得るのである(部分 的情報によって、当該個人に関する虚像が形成 され、そのような予断に基づく意思決定がされ る恐れがある。)。しかも、このような個人情 報の収集及び保有等を警察組織が行った場合に は、その利用のされ方(本件ではこの点自体も 明らかではないが。)によっては、正確性を欠 く情報(誤った情報、不十分な情報、最新のも のではない古い情報等)に基づき、監視の対象 とされたり、犯罪捜査の対象として取り上げら れたりして、誤認逮捕等の身柄拘束が生じる可 能性も否定できないのである。
さらには、公権力から誤った情報(部分的情 報のみが提供されることも含む。)が当該個人 に関係する第三者に提供されれば、当該第三者 は、誤った情報に基づく意思決定(部分的情報に基づいて虚像が形成され、これに基づいて意 思決定されることも含む。)をし、当該個人に 対して行動することになってしまうという弊害 も生じ得るのである。
このように記載されております。
○本村伸子
ありがとうございます。とても大事な視点が書かれた判決だというふうに思います。
今、最高裁に紹介をしてもらったこの判決文のような視点をしっかりと持って、捜査機関が個人情報の扱いについて、濫用がないよう慎重に扱うことが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
御指摘の事案は捜査機関ということで、警察の活動内容に関わる事柄ということで、個別の事件で、個別のことで、法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、捜査機関が犯罪捜査を行うに当たっては、個別具体的な事案に応じ、刑事訴訟法を始めとする法令であったり、あるいは判例等の趣旨を踏まえて、個人情報の取扱いについて適切に対処をしているものと承知をしておりますし、まさに今御指摘のように、こうした濫用であったりとか、そういったことはあってはならないということでありますし、これは慎重に取り扱う必要がある、そう私どもとしても考えております。
○本村伸子
今日皆さんにお配りをした資料の中に、判決の、憲法上の人格権としてのプライバシーの部分の一部を抜粋したものを配らせていただいております。先ほど最高裁に紹介していただいた部分は、ここの一ページ目のところです。
次に、二ページ目の部分に入りたいというふうに思いますけれども、この下線を引いた部分ですね、以下のような記述がございます。
「一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかである。」と。ないということですね。
次に、「情報収集活動については、法律上の明文の根拠がないのであり、基準となるべき具体的な規律がない」。
次、「警察による情報収集活動について、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのかなどを明確にした法律上の規律はないし、捜査機関の情報収集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判断ができる第三者機関も存在しない」。
次、「捜査機関による情報収集について、現状は、個人情報を安全かつ適正に管理するための何らの規制もないし、取得、保有及び利用について濫用防止のための何らの制度的保障もない状態なのである。」というふうに書かれております。
現行法上でも、全くこうした法的な保障がないと。そして、今回の法案においても、現行法の問題をそのまま内在したまま、電磁的記録提供命令という、よりリスクが高まるものが盛り込まれている。
そして、任意のときでも、令状を求めて令状を出された段階でも、あらゆる段階で濫用が起きないように、この捜査機関の情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなど、明確に規定する具体的な法律上の根拠が必要だというふうに考えます。
また、取得した個人情報の本人への通知ですとか消去などのルールを作ることや、捜査機関の個人情報の扱いの濫用を防ぎ、チェックする、独立した第三者の機関が必要だというふうに考えますけれども、こういう判決を真摯に受け止めるのであれば、やはりこういう法的な保障が必要だというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
こうした濫用を防ぐ、あるいは適正さ、これを担保する、まさにその方法論、どうするのかという話だろうと思います。
我々としては、捜査、これは、特定の犯罪の嫌疑が存在する場合にその犯人及び証拠を対象として行われるものでありまして、強制処分については、原則として、司法審査、それを経て行われるということであります。まさに捜査機関がそうした捜査の過程で収集する証拠、これは、特定の事件との関連性、これを有して、捜査目的の達成に必要なものとして収集、利用されているものと我々としては考えております。
また、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得をされた書類、これは、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものということで、現行法においては、こうした観点から、記録の保管、保存について適切な規律、これが設けられていると私どもとしては考えているところでございます。
法律上の根拠あるいは独立した第三者機関の設置ということでありますけれども、我々としては、現行法の規律ということでそれは十分に対応できていると考えているところでございます。
○本村伸子
先日の参考人質疑でも、日弁連の坂口参考人は、実務上、電磁的記録が入った携帯電話機やパソコンが差し押さえられる場合、令状に、本件に関係あると思料されるといった文言や、これらに関連する文書、物件といった包括的な記載があるということで、被疑事件と関連性の乏しい電磁的記録の差押えが行われているという現状があると。そして、指宿参考人も、包括的な差押えがなされている、現状が問題なのだというふうに言われているわけです。でも、大臣の認識は今でいいんだということで、やはりその認識を正していただきたいと思うんです。こういう判決もありますし、そして参考人の方々からも言われているわけです。
捜査機関の個人情報の扱いについて、濫用についてはどういう中身なのか、これは駄目ですよということも含めて、限定されるようにしっかりと法律で書いて、収集されて被害が出てしまった場合に、それを回復する措置、通知、消去、第三者機関、こうしたものをしっかりと明記をするべきだというふうに、是非、もう今すぐ検討を始めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○鈴木国務大臣
先ほど来申し上げておりますけれども、当然、濫用、これはあってはならないという中で、これは様々な捜査等々においても、この司法における裁判所、そういった判断の下での
ある意味で限定というものをかけている状況というものがあります。まさにこうした現場現場で、しっかりそういったこの趣旨というものを踏まえて、そういった執行をされることが肝要ではないかと考えております。
○本村伸子
是非今言ったものを早期に検討して、法律上、明記をしていただきたいというふうに思います。
次に、オンライン接見について伺いたいというふうに思います。
オンライン接見について、ニーズが高い地域から弾力的に実施していくことが妥当ということですけれども、ニーズの高い地域はどこだというふうに考えているのか、また、一施設当たりどのくらいの予算と増員が必要と考えているのかという点、伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
そのニーズが高い地域ということでありますけれども、今、関係機関あるいは日弁連と協議をしているところでありますが、どういった地域ということでいえば、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域、あるいは管内の弁護士数が少なくて、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域等々、そうした必要の高い地域からそうした場所というものを具体的には選定していくということになろうかと思います。
そして、一件当たりのそうした予算ということでありますけれども、それぞれ違う状況もありますので、これは一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば令和七年度の予算におきましては、九道県の十三地域で、こうした回線工事経費等の環境整備経費を計上しております。ならすと、一地域当たり平均三百万円程度ということであります。
○本村伸子
三百万円ぐらいだということで、予算的にはそれほど大きくかからないのではないかというふうに思っております。国家予算からしたら余りかからないというふうに思っております。やはりこういうオンライン接見ができるように、被疑者の方の権利もしっかりと守っていただかないと変な方に誘導されるということが、これも参考人質疑でも明らかになりましたので、そうしたことを早急に進めていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。