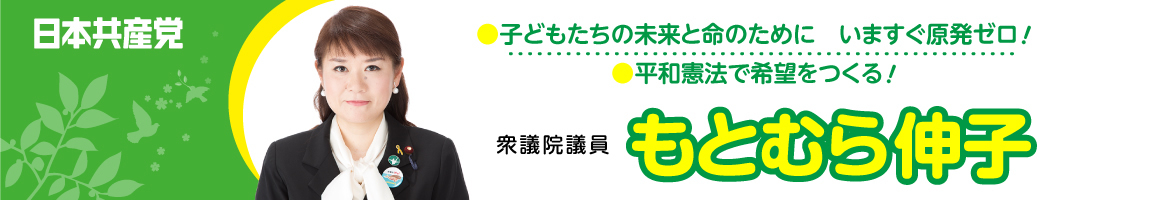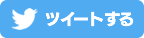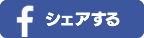衆院法務委員会で、法律上の同性同士の婚姻を認めない現行制度は憲法違反だとした五つの高裁判決を受け、法制化を強く求めました。
質問の映像へのリンク
同性婚「前に進めて」 高裁も「憲法13条違反」判断 2025.5.16
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。
まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。
これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。
同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
○本村伸子
少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。
今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。
今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。
判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨大な立法作業も必要となるとは言えないということも書かれている判決です。
私は、昨年の三月二十七日の質問の中で、この同性カップルの婚姻の平等保障がない中で、自分の存在意義を失ったり、あるいは喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々のお声や判決を紹介させていただきました。この苦難をなくすためにも制度を改善するべきだということを質問させていただきまして、その当時の小泉法務大臣が、国民的コンセンサス、理解が得られるように、法務省として力を尽くすというふうに答弁をしていただきました。しかし、大勢の方々がいて、様々な御意見があるということもおっしゃいました。
そこでお伺いをしますけれども、様々な意見があるというふうに言いますけれども、性的少数者への偏見や蔑視を考慮要素にすることはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。
同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。
ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。
○本村伸子
国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。
国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎない旨の主張や、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で法的な取扱いを異にしていないというふうに主張をしております。
しかし、名古屋高等裁判所は、その主張は採用できないというふうに判断をしております。婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことからすると、国側の主張は採用できないということを結論づけているわけです。
国や法務省は、婚姻の本質に関するこの判決の指摘を真摯に受け止めるべきだというふうに思います。
同性パートナーと婚姻ができない今の制度の下で、自分の存在意義を失ったり喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々に、異性と結婚できる、そういうことを言って傷つけることはあってはならないというふうに思います。こういう理不尽な主張はもうやめるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
いわゆる同性婚訴訟におきましては、婚姻制度に関する民法及び戸籍法の諸規定が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点が問題となっております。
被告である国は、その争点について、本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく、本件規定の文言上、同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから、この点に法令上の区別は存在しないと主張をした上で、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないと主張したものでございます。
委員御指摘の、同性愛者も異性との間で婚姻をすることができる、結婚することができるという部分でございますが、国がそのとおりの主張をしたというわけではなく、相手方である原告がその主張を基礎づける証拠として提出された文献の中に御指摘のような記載があることに言及したにとどまるものと承知をしております。
○本村伸子
こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。
二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。
その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。
○福田最高裁判所長官代理者
福岡高裁の判決の判断部分が示された部分ということでございますけれども、最高裁の方で特定をするというのが難しくございますので、特定していただければと思います。
○本村伸子
判決の十一ページ下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページの二行目、「いうべきである。」まで、また、十二ページの八行目、「性的指向は、」から、十二ページの十九行目まで、さらに、十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページの三行目、「いわざるを得ない。」まで、御紹介をいただきたいと思います。
○福田最高裁判所長官代理者
委員御指摘の部分のうち、判決文十一ページの下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページ二行目、「いうべきである。」までをまず読み上げさせていただきます。
憲法十三条は、婚姻をするかどうかについての 個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻 の成立及び維持について法制度による保護を受 ける権利をも認めていると解するべきであり、 このような権利は同条が定める幸福追求権の内 実の一つであるといえる。そして、上記のとお り、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みで あり、尊重されるべきものであることに鑑みる と、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠か すことのできない権利であり、裁判上の救済を 受けることができる具体的な権利であるという べきである。
このように記載されております。
続いて、判決文十二ページ八行目、「性的指向は、」から、十二ページ十九行目、「重大である。」までを読み上げさせていただきます。
性的指向は、出生前又は人生の初期に決定され るものであって、個々人が選択できるものでは なく、自己の意思や精神医学的な方法によって 変更されることはないところ、互いに相手を伴 侶とし、対等な立場で終生的に共同生活をする ために結合し、新たな家族を創設したいという 幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合 と同性である場合とで何ら変わりがないから、 幸福追求権としての婚姻の成立及び維持につい て法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、 同性のカップルのいずれも等しく有しているも のと解される。にもかかわらず、両当事者が同 性である場合の婚姻について法制度を設けず、 法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対 象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する 者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことに ほかならず、配偶者の相続権(民法八百九十条 )などの重要な法律上の効果も与えられないの であって、その制約の程度は重大である。
このように記載されております。
最後に、判決文十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページ三行目、「いわざるを得ない。」までを読み上げます。
したがって、本件諸規定のうち、異性婚のみを 婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制 度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対 象とすることができず、同性の者を伴侶として 選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立 及び維持について法制度による保護を受ける権 利に対する侵害であり、憲法十三条に違反する ものといわざるを得ない。
このように記載されております。
○本村伸子
ありがとうございます。
高等裁判所の段階では、もう五つの高等裁判所で満場一致で違憲という判断が下されております。同性パートナーと結婚をしたいという方の幸福追
求権、異性パートナーと結婚したいという方と同じように保障するべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、前に進めていただけないでしょうか。
○鈴木国務大臣
同性婚について、これが認められないということによって負担を感じていらっしゃるそういった方々、その声や思い、これは十分に承知をしております。
その一方で、同性婚制度を導入ということになりますと、親族の範囲、あるいは、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる、まさにそういったものであると思います。国民一人一人の家族観と密接に関わるものであります。
そのため、やはり国民各層の御意見、あるいはこの国会、立法府における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向等、引き続き私どもとしては注視をしていく必要があると考えております。
○西村委員長
本村さん、時間ですので、御協力をお願いします。
○本村伸子
石破総理も、等閑視することはいたしませんということで答弁をしておりまして、放置することはしないんだという答弁をしております。
是非前に進めていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。