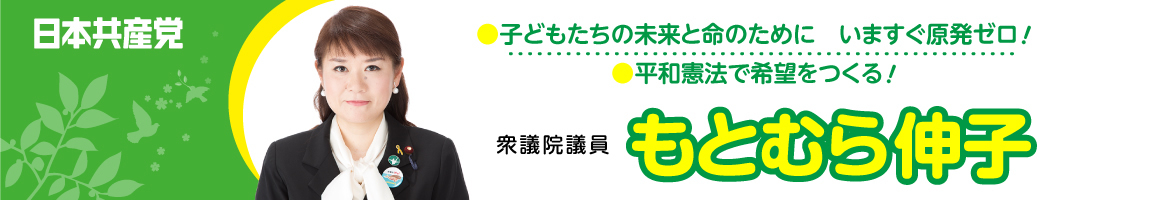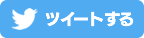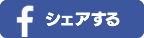判例で運用されていた譲渡担保を法制化する新法が衆院法務委員会で、全会一致で可決しました。
労働者・事業者の保護について質問しました。
質問の映像へのリンク
譲渡担保法案について 労働者・事業者保護を 2025.5.21
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
譲渡担保法案について質問いたします。
今回の法案は、事業のための資金調達、融資を受けるために事業に必要な機械などを譲渡して財産権を移してお金を借りて、お金を返したらその機械の財産権を元の所有者に戻すという慣行で行われていた譲渡担保、集合動産譲渡担保というものを法的に整理した法案だというふうに思いますけれども、機械などの場合は譲渡担保といい、倉庫の中の商品のような場合は集合動産譲渡担保ということになっております。
お金が返せなくなった場合、債務不履行に陥った場合にどこかに処分されてお金に換えられてしまう可能性があります。そうなると、会社、法人が倒産ということとなり、そのときに未払い賃金、退職金、賞与など、労働者への支払いができなくなるおそれがあります。
こうした労働債権をちゃんと支払うためにどのような手だてを取っているのかという点をまず確認をさせていただきたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しているところでございます。
すなわち、これらの担保権が実行された場合におきまして、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
具体的には、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額とのいずれか大きい方の額を超えて被担保債権が消滅した場合に、譲渡担保権者はその超える額を組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む一般債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものであると考えております。
○本村伸子
法案では、集合譲渡担保と譲渡担保で規律が違うわけです。集合債権譲渡担保権の場合のみ一割以上ということで、労働債権のために確保をされるというふうに思います。
例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労働者によって運用されているという場合は、労働者の寄与の程度が大きく、集合動産譲渡担保と同様に労働債権分として保護するべきだというふうに考えますけれども、特定物を対象とする譲渡担保と集合譲渡担保とを具体的にどのように区別をするのかという点、お示しをいただきたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約は、動産の種類、所在場所その他の事項によって定められた範囲によって特定された動産を一体としてその目的とするものをいうとしております。これは、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけでなく、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されている必要があることを意味しております。
そのため、譲渡担保契約の目的が現に存在する複数の動産のみを担保の目的としている場合には、個別の動産を目的とする譲渡担保契約でありますが、現に存在する動産に加えまして、将来の動産についても属し得るものとしてその範囲が定められている場合には、集合動産譲渡担保契約に該当することになると考えております。
○本村伸子
そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
個別の事情あるいは個別の契約の内容にもよるかと思いますが、将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかというのが区別の基準になると考えております。
○本村伸子
譲渡担保の場合も労働者が寄与する程度がかなり大きいというものもあるというふうに思います。譲渡担保の場合でも労働債権をちゃんと確保するべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
○鈴木国務大臣
今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。
譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。このために、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。
譲渡担保権の範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかについては、譲渡担保契約における譲渡担保権の目的財産の定め方によるところがございますので、契約上定められた目的物の範囲に既存の動産だけではなくて将来における動産が含まれ得ると解釈をされる場合、その場合に、集合動産譲渡担保権に該当するということで、組入れ制度が適用されるということになるというのが私どもの見解でございます。
○本村伸子
労働債権についてはしっかりと、働く方々と家族、あるいは命、暮らしを守るためにも確保のための対策を強化していただきたいというふうに思っているわけですけれども。
今回、財産の価値の一割を倒産財団のために確保をして組み入れる制度ということで、一割以上というふうには先ほども答弁がありましたけれども、十分に労働債権の弁済が図られるのかという問題があります。これだけでは労働債権の保全には不十分と言わざるを得ないというふうに思います。
労働債権などの一般債権者への弁済の実効性を高めるためには、倒産財団、破産財団への組入れ対象の範囲の拡大ですとか新たな供託制度による保全対策の強化、これは先ほど来御議論もありましたけれども、改めてやはりこうした対策が必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
今回の譲渡担保法案が規定をする組入れ額、ここは一般債権者に対する弁済原資を確保をしつつ、担保価値の減少による融資実務への影響、これについても配慮をしたものでありまして、まさにその実効性ということを期待できると私どもとしては考えているところであります。
破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場合には、担保価値の減少による融資実務への影響に鑑みると、この割合を増加させることについては慎重な検討がやはり必要であろうと我々としては考えております。
また、お尋ねの新たな供託制度による保全対策、これは倒産手続開始前の時点であらかじめ組入れ額を供託をさせる、そういった制度ということかと存じますが、そのような制度については、設定者について倒産手続が開始されるまでは組入れ義務は発生をしていない、債務が存在をすることを前提とする弁済供託を義務づけることはできない等々の課題があるところでありまして、その導入についても慎重な検討が必要ではないかと考えております。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、組入れ制度の内容について周知に努めていく、そして同時に、施行後は、譲渡担保法施行後の組入れ制度の運用状況等、これをしっかりと注視をしてまいりたいと考えております。
○本村伸子
働く方々と家族の命と暮らしを守るために対策を強化していただきたいと思います。
労働債権は、ほかの債権者や国の社会保障制度の請求権に優先して支払われる労働債権の保護を確実にするためのILO百七十三号条約、これも早期に批准をするべきだということを私からも強調をさせていただきたいというふうに思います。
次に、資金の回収、保全のための金融機関が財産を根こそぎ回収するという手段に使われるおそれについてですけれども、それを一定抑えるために、私的実行の完了までの一定の猶予期間を創設し、着手から二週間を経過するまでは実行が完了しないものとしております。
お金を借りている事業者への通知がなされたとしても、当事者の方がやむを得ない事情で通知されたということが分からない、そういう場合もあると思います。私も実際いろいろな御相談を受ける中で、ポストに通知が入っていたけれども別の場所にいたのでそれが知らなかった、でもそのうちに差押えされてしまったという御相談も受けたんですけれども、そういうこともあるかというふうに思います。
そういう場合もあるということで、二週間の猶予期間では設定者の保護には不十分ではないかというふうに考えますけれども、その点、御所見を伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣
今回の法案におきましては、今御指摘のように、私的実行の効果が発生をするには、設定者に対する通知、ここから二週間が経過をすること等が必要であるとされているところであります。
この通知の効力が発生をするには、通知が設定者に到達をすること、これはすなわち通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれること、これが必要となると私どもとしては認識をしております。
その趣旨として申し上げると、この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。まさにそれは設定者の事業再生の利益を保護するための実効性の図られた制度と私どもとしては考えているところであります。
その上で、今、通知が了知して、どういう状況なんだということでありますけれども、どの時点で通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたと評価をして二週間の期間の起算をするかということについては、これは個別具体的な事情もありますので、そこに応じて裁判所において適切に判断をされると私どもとしては考えております。
○本村伸子
会社更生ですとか事業再生ができるように、是非柔軟に解釈をするということでお願いをしたいというふうに思います。
法案は、新しい融資制度を創設するものではなく、実務上、判例法理で運用されてきた既存の譲渡担保制度を法制化するものにすぎないというふうに思います。中小企業、小規模事業者の皆さんに関しては、無担保で融資をすることが今広がっている現状があります。
本法案は、無担保で融資を受けられない事業者が融資を受ける手段とはなり得るというふうに思いますけれども、本来であれば、無担保融資制度の枠組みを拡大するということが最優先であるべきだというふうに思います。特に、今、トランプ関税の影響が大変心配をされております。
私は、愛知県豊田市の出身で、住んでおりますけれども、自動車産業を含め様々な産業、電機産業なんかはリストラの計画が様々出ております。本当に中小・小規模事業者の皆さんのことが心配されるわけでございます。地元の中小・小規模事業者の団体の皆様から様々お話も伺っておりますけれども、今、中小・小規模事業者の皆さんを守る思い切った支援が必要なのではないかというふうに考えますけれども、経済産業副大臣、そして大臣にお伺いをしたいと思います。
○西村委員長
大串経済産業副大臣、時間が参りますので、簡潔に。御協力お願いします。
○大串副大臣
中小企業の資金繰り円滑化のために、日本公庫等による貸付け、そして民間金融機関から借入れに対する信用保証を通じた金融支援を実施しております。
無担保融資に関しましては、日本公庫等により貸付金額全体のうち大半は無担保で融資をしております。また、信用保証においても、一社当たりの平均利用額は二千四百万程度に対して、八千万円を上限として無担保で保証付融資を受けられる枠を設けているところでありまして、まずはこうした既存の制度の活用を図っていくところでございます。
また、お尋ねの米国の関税措置の影響を受けて、事業者に対しては、政府としては、短期の資金繰り支援策として、日本公庫の低利融資制度であるセーフティーネット貸付けの利用要件の緩和を講じているところでもありまして、本融資制度も無担保で利用が可能となっております。
経産省としては、引き続き、中小企業を取り巻く状況を注視しながら、適切な支援を実施してまいります。
○鈴木国務大臣
担保付融資において、要は、担保を提供しない場合と比較して借り手が有利な条件で融資を受けられる場合、それも多いこともありますので、まさにそれはメリット、デメリット両方あると思います。
そういったことで、多様な資金調達の選択肢の存在、これは私どもとしても大事だと考えておりますので、企業の円滑な資金調達、これが促進されるように、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
○西村委員長
本村さん、時間ですので、終わってください。
○本村伸子
はい。
ありがとうございました。