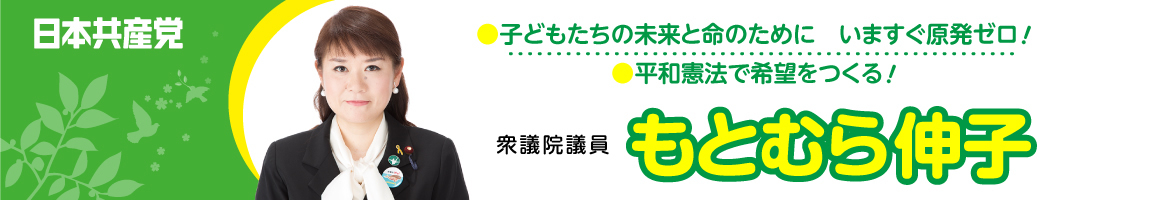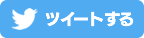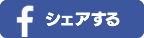選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案などの質疑が衆院法務委員会で始まりました。
同委で選択的夫婦別姓導入の法案の質疑が行われるのは1997年以来28年ぶり。
選択的夫婦別姓を求める請願が国会に提出されて50年、当事者らとともに法改正を求め続けてきたと述べ、同制度の実現を訴えました。
質問の映像へのリンク
Roblox コミュニティのご紹介 ナビゲーションをスキップ 検索 作成 アバターの画像 選択的別姓今度こそ 選択的夫婦別姓法案について 2025.6.4
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
日本共産党は、選択的夫婦別姓について、法制審の答申のもっと前から民法の改正を求めてまいりました。それは請願が出されて五十年というように、当事者の皆さんの声があったからです。
一九九六年法制審の答申後、ほかの野党の皆さん、当時の民主党の皆さんや社民党の皆様と選択的夫婦別姓を含む民法の改正案を提出し、私が秘書をしておりました八田ひろ子参議院議員がその提出者として法案に関する答弁もしたこともございます。野党でこの間も一緒に出してきた選択的夫婦別姓の法案では、夫婦が同じ名字でも別の名字でも選べるというもの。そして、先ほど来御議論がありますように、結婚するときに産むことを前提としない、子を持つことを前提としない、そのためにも、子の名字は出生時に父母の協議で決める、そして兄弟で名字が異なることはあるということ。そして現行法でも、家庭裁判所の許可を得て変更という原則を維持しつつ、届出のみで変更可能となる場合も追加する、そういう内容を含んだ法案でございました。
日本共産党は、これまで一緒に出してきた法案がよいというふうに思っておりますけれども、しかし、立憲民主党の皆さんや国民民主党の皆さんが、与党の議員も含めて、より多くの人の賛同を得られるようにと今回の法案をまとめたのだというふうに理解をしております。そういう意味では、選択的夫婦別姓の実現のために、私たちも協力をしていきたいというふうに思っております。
それで、まず前提なんですけれども、一、二、三は飛ばして、四番から申し上げたいというふうに思います。
四番目に通告した内容ですけれども、改めて、法制審議会民法部会身分法小委員会等の議論の中で、通称使用の法制化、C案は否定をされたということですけれども、先ほども議論がありましたけれども、今度は大臣から、その理由について御説明をお願いしたいと思います。
大臣にお願いをしました。せっかく参加をしているのに、大臣お願いします。大臣、せっかく、これしかないのでお願いします。
○鈴木国務大臣
議論の経緯ですので、これまでのしきたりで、参考人の方から御答弁させていただきます。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしておりますが、委員御指摘のC案につきましては、呼称という概念を用いて、事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること。氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な問題が新たに生ずること。この民法上の呼称は、現在戸籍事務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあることから、長期的な展望に立った氏の制度として採用することは、相当ではないとして採用されなかったものと承知をしております。
○本村伸子
このようなことで、法制審では、通称使用の法制化は否定をされました。
日本維新の会の法案では、通称使用の法制化ですので、この法制審の指摘をされた問題をクリアしているのかという点も問わなければならないというふうに思います。
まず、また前提ですけれども、名字と名前がセットの氏名について、一九八八年の最高裁の判決の中で、氏名は、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと言うべきであるということが最高裁の判決の中で書かれております。
この法案を提出されている三党それぞれの提案者に、氏名とは何かという点、まず伺いたいと思います。
○米山議員
時間も短くですので繰り返しませんけれども、私もまさに、その最高裁判決そのものだというふうに思っております。氏名とは、個人を同定する、英語で言えばアイデンティファイする機能を有し、それゆえ社会的存在である人間にとって、自分が自分であると感じるアイデンティティーの根源の一つになっているというふうに考えております。
○藤田議員
最高裁判決においては、氏名は、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものであるというのが示されていますが、そのとおりだと思います。
○鳩山(紀)議員
同じでございます。
○本村伸子
ありがとうございます。
日本維新の会の法案では、通称使用を法制化することになりますが、婚姻前の名字を単独で使うと届出した場合には、戸籍は夫婦が同じ名字、それ以外は全て結婚する前の名字と名前、いわゆる通称で生活することができるというふうになっていると思います。
例えばということですけれども、法制審の案で例示をされた名前をお借りをいたしますと、私が結婚をして、結婚する前の名字、氏名、乙野梅子さんというのを通称使用するとする。維新さんの案では、パスポートも免許証も健康保険証もみんな、乙野梅子さんのみが書かれる。周りの皆さんも、私が乙野梅子さんだと認識をしてくださっている。そして、私も、乙野梅子さんと認識をされ、呼ばれることに、個人として尊重されているというふうに感じている。一方、戸籍の方は甲野梅子さんというふうになっておりまして、周りの人はほとんど知らない甲野梅子さんが名字、本名だということになっております。
生まれ持った乙野梅子さんの方が社会から個人として識別、特定され、自分としても、乙野梅子さんが私だと感じ、個人として尊重されていると感じるという意味で、一九八八年の最高裁判決の氏名ということに合致するというふうに思います。
こういう場合、戸籍のみにある甲野梅子さんという名字は一体どういうものだというふうに考えているのか、維新の提案者に伺いたいと思います。
○藤田議員
お答え申し上げます。
お尋ねは恐らく、維新案が実現する、そのような状態において、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏であるところ、戸籍氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですが。
確かに、この場合、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは通称使用する旧氏でありますけれども、そもそも、先ほど言及しました最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素である家族、先ほど言及を割愛しました、ごめんなさい、社会の構成要素である家族の呼称としての意義も存在します。
したがいまして、この場合の戸籍氏にも、夫婦から子に受け継がれ、家族全体のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義がなお確実に存在すると言えまして、実際上も、親族の集まりなどの私的な場面においては、これをいわゆるファミリーネームとして使用することも当然に可能であります。
維新案は、このような家族としての呼称の意義、つまり、ファミリーネームはあった方がいいんじゃないか、そういう考えを極めて重く見て立案したものでございます。
○本村伸子
二〇一五年の最高裁の判決のことを言われたというふうに思いますけれども、その判決は、やはり個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだと批判をされている判決でございます。
一般社団法人の「あすには」の皆様が事実婚の当事者の方々に調査をした。そうしますと、五十八万七千人という方々が法律婚を待っておられると。こういう当事者の方の声に応えていくべきだというふうに思います。
また、新日本婦人の会の皆様が今年一月に二週間で取ったアンケート、三千九百七十九人の方々の声から、アイデンティティーに関するところをピックアップいたしました。
二十代の女性の方、自分の名字にアイデンティティーを持ち、改姓したくない、パートナーにも改姓を強制したくない、三十代の女性の方、旧姓の私が本当の私だと思っている、夫の姓に改姓して、旧姓の時代の私を喪失したような気持ちになっているというお声や、三十代の女性の方、自分が結婚をしたとき名字を変えたくなかった、これまでのキャリアとアイデンティティーの崩壊を感じ、泣いた、こういうふうに書かれております。
こういう苦しんでおられる方々がいるのに、アイデンティティーの喪失は我慢しろということでしょうか。維新の方にお伺いしたいと思います。
○藤田議員
委員御指摘のアイデンティティーに関しましては、維新案提出者としてももちろん大切な要素であると認識しており、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活など社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになっているため、アイデンティティーの喪失といった懸念につきましては解消され得るものも一定あるんだろうと思います。
ただし、委員のおっしゃることはよく分かります。だからこそ、私らも丁寧な対応をしたいなというふうに思っていまして、私もこれは提案者で責任があるので、いろんな方に聞きました。
例えば、芸能人や国会議員でも通称を使っておられて、アイデンティティーはどちらですかと言うと、ふだん使っている名前とおっしゃる方も結構いまして、それはやはり、ふだん使われて、ふだん呼ばれて、そういうふうなものにアイデンティティーを持たれる方もいらっしゃるし、それで満足される方も結構いて、僕らの案で十分だという方も、推進派の方にも結構いるなということは認識をしました。
ただ一方で、戸籍にその記載があることがすごく違和感があるという方が一定残るということについての御主張だと思うんですけれども、それは重く受け止めたいと思いますが、我々はそういったことも踏まえて、やはり幅広い合意形成の中で、戸籍制度の根幹部分を残しながら、実務上のお困り事というのを全て解消する、つまり、多くの人に喜んでもらえる、そういう一歩を踏み出したいという思いで立案したものでございます。
○西村委員長
本村さん、時間が来ていますので、御協力、お願いします。
○本村伸子
はい。
名字を変えたくなかったと泣いてしまわれる方々もいらっしゃるということで、個人として尊重されること、個人の尊厳、本質的平等を実現する、そういう立場に維新さんも立っ
ていただいて、一歩前に進んでいただいて、一緒に合意形成できたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。