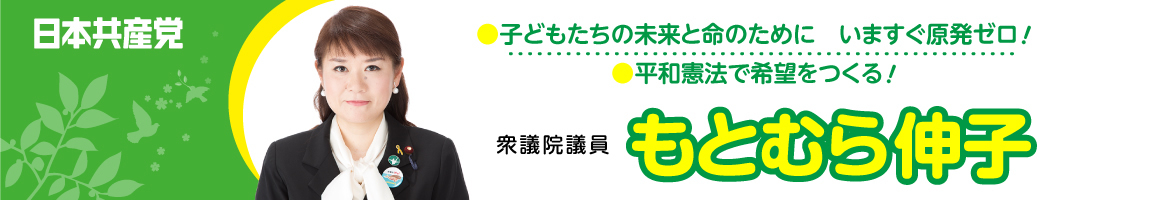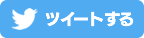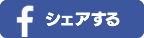衆院法務委員会で、2015年に最高裁が現行民法の夫婦同姓規定を合憲とした判決に際し憲法違反と主張した女性裁判官の意見を示し、その重みを国会がくみ取り、「早急に選択的夫婦別姓の実現を」と呼び掛けました。
同判決に際し、岡部喜代子最高裁裁判官(当時)は現行規定が「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない」などとして、憲法24条に違反するとの意見でした。本村氏は、15人の裁判官のうち5人が違憲とし、うち3人の女性裁判官は全員が違憲だったと指摘。最高裁の男女比率が平等でないもとで出された同判決を乗り越え、別姓制度を実現するよう求めました。
質問の映像へのリンク
議事録
本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、選択的夫婦別姓に関する最高裁の二〇一五年の判決の中で、多数派意見に対して反対の意見、憲法に反するとの意見が書かれています。岡部喜代子裁判官の意見のうち、判決十八ページから二十ページのイとウとオを御紹介をいただきたいと思います。最高裁、お願いします。
馬渡最高裁判所長官代理者
委員御指摘の部分、これらはいずれも岡部喜代子裁判官の意見が記載されている部分でございますが、このうち、まず、裁判所ホームページ掲載判決文十八ページ七行目、「次に、」から二十二行目末尾までを読み上げます。
次に、氏は名との複合によって個人識別の記 号とされているのであるが、単なる記号にとど まるものではない。氏は身分関係の変動によっ て変動することから身分関係に内在する血縁な いし家族、民族、出身地等当該個人の背景や属性等を含むものであり、氏を変更した一方はい わゆるアイデンティティを失ったような喪失感 を持つに至ることもあり得るといえる。そして、 現実に九六%を超える夫婦が夫の氏を称する婚 姻をしているところからすると、近時大きなも のとなってきた上記の個人識別機能に対する支 障、自己喪失感などの負担は、ほぼ妻について 生じているといえる。夫の氏を称することは夫 婦となろうとする者双方の協議によるものであ るが、九六%もの多数が夫の氏を称することは、 女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活に おける立場の弱さ、種々の事実上の圧力など様 々な要因のもたらすところであるといえるので あって、夫の氏を称することが妻の意思に基づ
くものであるとしても、その意思決定の過程に 現実の不平等と力関係が作用しているのである。 そうすると、その点の配慮をしないまま夫婦同 氏に例外を設けないことは、多くの場合妻とな った者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別 機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負 担を負うこととなり、個人の尊厳と両性の本質 的平等に立脚した制度とはいえない。
このように記載しております。
また、委員御指摘の部分のうち、判決文十九ページ一行目、「そして、」から十行目末尾までを読み上げます。
そして、氏を改めることにより生ずる上記の ような個人識別機能への支障、自己喪失感など の負担が大きくなってきているため、現在では、 夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるためにあえて法律上 の婚姻をしないという選択をする者を生んでい る。
本件規定は、婚姻の効力の一つとして夫婦が 夫又は妻の氏を称することを定めたものである。 しかし、婚姻は、戸籍法の定めるところにより、 これを届け出ることによってその効力を生ずる とされ(民法七百三十九条一項)、夫婦が称す る氏は婚姻届の必要的記載事項である(戸籍法 七十四条一号)。したがって、現時点において は、夫婦が称する氏を選択しなければならない ことは、婚姻成立に不合理な要件を課したもの として婚姻の自由を制約するものである。
このように記載されています。
最後に、判決文二十ページ八行目、「以上の」から十二行目末尾までを読み上げます。
以上のとおりであるから、本件規定は、昭和 二十二年の民法改正後、社会の変化とともにそ の合理性は徐々に揺らぎ、少なくとも現時点に おいては、夫婦が別の氏を称することを認めな いものである点において、個人の尊厳と両性の 本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国 会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており、 憲法二十四条に違反するものといわざるを得な い。
以上でございます。
本村伸子
ありがとうございます。
この最高裁の判決、多数派意見に対する岡部喜代子裁判官の反対意見に、桜井竜子裁判官、鬼丸かおる裁判官、女性の裁判官が同調するということが書かれております。十五人の最高裁の裁判官のうち五人が違憲との意見を示し、三人の女性裁判官は全員が違憲といたしました。もしも二〇一五年の最高裁の裁判官の男女の割合が、女性が十二人、男性が三人、こういう状況であったら、あるいはもっと多様性がある状況であったら、現行の今の法制度は違憲という判決が多数だったかもしれません。
まず、最高裁のこの構成が平等ではない。そして、国会の構成も平等ではない。閣僚の構成も平等ではない。そういう構成の中で、構造の中で憲法違反と三人の女性の裁判官が意見をされたその重みを是非この国会が酌み取り、二〇一五年の判決を乗り越えて早急に選択的夫婦別姓を実現するべきだというふうに考えます。
六月十一日の答弁の中で、選択的夫婦別姓の実現によって他人の人権を侵害することはないとの答弁、三人の、三党の皆さんからございました。そうであるのであれば、選択的夫婦別姓を求める方々の婚姻の平等を最大限保障するべきだというふうに考えますけれども、三党の皆さんに伺いたいと思います。
米山議員
おっしゃるとおり、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度は、選択でございますので、全く他人の人権を侵害するものではございません。
ですので、議員御指摘のとおり、他人の人権は侵害しませんし、また、それを求めているような人にとっては、人権の保障を厚くするものですので、是非、今国会で成立させていただきたいと考えております。
藤田議員
お答え申し上げます。
維新案の実現によっても、婚姻の前後で同じ氏を社会生活上は使い続けることができるようになるわけですから、選択的夫婦別氏制の導入を求める方々の中にも一定数の方の理解を得られると考えて、今回の法案を提出しております。
また、先日お答えしたことと重なりますが、たとえすぐさま他者の人権を侵害しないとしても、選択的夫婦別氏制を導入することについては国民の間にも様々な慎重意見があることもまた事実でありますので、人権を侵害しない制度なら何でもすぐに社会全体の制度として導入してよいということではないだろうと思います。
鳩山(紀)議員
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、国民民主党が導入しようとしております選択的夫婦別氏制は、夫婦同氏を希望する夫婦に不利益を与えるということは基本的にありませんで、夫婦別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるというものでございます。
選択的夫婦別氏制が導入されますと、婚姻の当事者が夫婦同氏と別氏を選択することができまして、それぞれの意思が最大限尊重されるということによりまして、委員御指摘の婚姻の平等が実現されることになるというふうに考えております。
本村伸子
参考人質疑でも、今の藤田提案者のお話でもございますけれども、社会のコンセンサスという言葉がございます。
そうしますと、少数者の方々、マイノリティーの方々はいつまでたっても人権が保障されないということになってしまいますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
藤田議員
お答え申し上げます。
何か、少数者の人権を軽視せよという話ではありません。これは制度設計の話でありまして、いろいろな御要望がありますし、その思いの強さというのは様々ありますけれども、制度全体、しかも、例えば民法の改正、戸籍法もそうですけれども、国民全体に関わる制度であります。
ですから、様々、御意見を慎重に受け止めながら、これまで議論にも上がってきました世論調査や国会での審議、そういったものも含めまして、我々がどういう意思決定をするかという非常に、あるべき姿がそれなんだろうと思いますから、決して、委員がおっしゃられているように、一人の御主張、それを黙殺してよいのかというような、そういう極端な話ではなくて、制度設計は常にそういうものだというふうに認識をしております。
本村伸子
今、婚姻の平等が保障されていない現実があるわけです。幸せに結婚しようという方を応援するということが、それが人権を保障することにもつながりますし、是非進めていきたいというふうに思っております。
朝日新聞の六月十一日に、選択的夫婦別姓訴訟の弁護団長をこれまで務めてこられた、一次、二次と務めてこられた榊原富士子さんのお言葉がございます。
選択的夫婦別姓の機運が高まるたびに必ず顔を出すのが通称の法制化です、旧姓を使いやすくするものではありますが、別姓阻止のツールとして働いているのです。別姓のストッパーとしての通称使用が最も利いているのは裁判でしょう、一五年に最高裁大法廷は現行制度を合憲としました、判決には、通称使用が広まることにより不利益は一定程度緩和され得ると短く書かれています、この部分に裁判官の、通称使用でいいじゃない、大した問題じゃないでしょうという思いが凝縮されているように感じました。今国会で二十八年ぶりに選択的夫婦別姓の法案が審議入りしました、通称使用の法制化ではなく、緻密に議論された九六年の法制審議会の答申案とほぼ同じ法案を立憲と国民民主党が提出しています、与党の賛成派とも力を合わせて成立させてほしい、もうこれ以上回り道をする必要はありません。
別姓を求める人の多くには、自分の名前を通称や旧姓にしないでほしいという思いがあるということも重く受け止めていただきたいというふうに思っております。
先ほどもコンセンサスというお話をさせていただきましたけれども、参考人質疑でも世論調査に関する議論がございました。
大前提でいま一度伺いたいんですけれども、世論調査の結果、たとえ少数であっても人権は保障されなければならないというふうに考えますけれども、三党の皆さんに改めて伺いたいと思います。
米山議員
お答えいたします。
人権につきましては、全ての国民に生まれながらにして保障されるべきものでございますので、世論調査の結果、少数であるから人権が保障されなくてもやむを得ないと考える方がおられるなら、それは人権という考え方を誤解していると指摘させていただきます。
現在議論されている選択的夫婦別姓を可能とする法案につきましても、私は、制度論の観点から、世論調査を参考にするということは特段否定いたしませんが、人権保障という観点からは、世論調査における多寡がそのまま法案導入の必要性、妥当性の判断につながるものではないと指摘させていただきます。
藤田議員
お答え申し上げます。
世論調査の結果にかかわらず、私たちといたしましても、基本的人権が全ての国民に保障されるべきものである、そのことについては当然ながら異論はございません。
また、我が党に対しまして、特に重ねてのお尋ねでありますけれども、維新案は、選択的夫婦別氏制とは異なる方法で、婚姻により氏を改めた方の困り事をしっかりと解消すること、その人格的利益を保護したいと考えているものでございます。
この点、十日の参考人質疑でも、実務的な話とアイデンティティーは非常に密接にリンクしているというお話もありました。維新案が施行されれば、そうした実務上の不便が全て解消されますので、おのずとアイデンティティーの喪失感についても緩和されることと想定をしております。
もちろん、先ほど来申し上げているように、それでも一〇〇%の納得を得られない方が一定数おられるというのは、これは提出者としても認めるところでございますが、それらの希望、要望を今後どのように制度として取り入れられるかどうかということについては引き続き国会で議論していくべきだと思います。
先ほどちょっとありました、我々の案、すなわち、旧姓使用の法制化や拡大というのは、別姓阻止のツール、潰しているためのツールみたいな、そういう言い方をされている方又は思われている方もいらっしゃると思いますが、私は、過去にそういう発言を一度もしたこともありませんし、そういう意図もございません。
逆に、フェアに申しますと、立憲さんの案が戸籍制度を全て破壊する破壊工作のツールであるとも私は申し上げていません。ただ、戸籍の意味合いや原則が変わるという、そのことをどの程度重く受け止めるかという、こういうフェアな議論を私はすべきだと思います。
鳩山(紀)議員
短めにお答えいたします。
立憲の提出者の方からもお答えがあったとおり、人権につきましては、当然ながら、全ての国民が生まれながらにして保障されるべきものということで、世論調査の結果に左右されるものではございません。
時に人権と人権が衝突するような場面もございますけれども、そういったときも、十分に議論をして、そして多くの方々に納得していただけるような解決策をお示しできるように努力を重ねていくことが重要だと考えております。
本村伸子
人権の問題ですので、世論調査でどうこうということは、それを主に議論するべきではないというふうに私は考えております。
女性差別撤廃条約では第十六条に明確に、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取るものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保すると書かれています。「(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」「(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」
このことを本当に完全に実施をしようと思ったら、選択的夫婦別姓ということになると思いますけれども、国連の女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓についてどのような勧告がこれまで出されてきたのか、お示しをいただきたいと思います。
山本政府参考人
お答え申し上げます。
夫婦の氏の選択に関しては、女子差別撤廃委員会からこれまで四度の勧告が出されているところでございます。
直近においては、昨年十月に公表されました我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に関する第九回政府報告を受けた女子差別撤廃委員会の最終見解におきまして、申し上げます、「女性が婚姻後も婚姻前の姓を保持できるようにするために、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正する。」というような勧告がなされているところでございます。
本村伸子
三党にお伺いしたいんですけれども、なぜ女性差別撤廃委員会から四回も勧告を受けているというふうに考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
米山議員
お答えいたします。
それはまさに、選択的夫婦別姓を導入することが実質的な男女平等を実現するために必要かつ必須であるにもかかわらず、それが実現していないからだというふうに考えております。
現在の夫婦同姓制度は、法律上は夫又は妻のどちらの姓を選んでもよいことになっており、形式的には男女平等となっているものの、実際には約九五%の夫婦において妻が姓を改めております。このような現状は、両性の本質的平等という観点に照らして決して望ましい状況とは言い難いと言えます。
この点、立憲案は、現行の夫婦同姓制における男女間の不平等を解消すべく、民法という実体法の中で完結する形で、夫婦別姓という新たな選択肢を追加することで、実質的な男女平等を実現し、夫婦同姓を望む当事者をも含めた各個人の選択を尊重しようとするものであり、両性の本質的平等という女性差別撤廃条約の要請に完全に合致しているものと考えております。
藤田議員
お答え申し上げます。
国連女性差別撤廃委員会の勧告及びまつわるその御主張につきましては、私は、個人的には相当意見があります、違和感もあります。
特に皇室典範と男系男子等にも様々触れてこられたこの委員会のそういう勧告、その一連の勧告であると受け止めておりますが、そこの見解は今日は提出者でありますので控えますが、勧告が何度も出されているということの御質問にお答えすると、平成八年の法制審議会答申以降、選択的夫婦別氏制を導入するのか、それとも通称使用の法制化で十分であるのかという、そういった実務的な議論をおざなりにし結論を先送りにしてきた立法府、そして関わってきた政治家の責任であると考えております。
円議員
委員御指摘のとおり、選択的夫婦別氏について、平成十五年以降、四回にもわたって日本政府は国連女子差別撤廃委員会から勧告を受けております。
先ほど外務省の方からも御説明がありましたが、昨年十月には、またこの見解、四回目を受けまして、国会でも女性たちの団体が大勢集まって、何とか、特に言われております選択的夫婦別氏制について実現をしてほしいという要望があったことも、私も集会に出て承知しております。
このときにも、夫婦に同じ氏を使用することを求め、事実上、女性に夫の氏をしばしば強いることとなる民法第七百五十条を改正する措置が取られていないことに関して、特に懸念を持って勧告がされているわけでございますよね。
この点につきましては、先ほども申し上げましたが、平成八年に法制審議会が答申を出したのでございますから、まずは法務省が責任を持って検討を進め法案を提出するべきであったと考えております。
また、平成八年以降継続的に野党が選択的夫婦別氏導入法案を提出していたにもかかわりませず、自民党が残念ながら審議に応じてくださいませんでした。また、平成八年の法制答申以降、選択的夫婦別氏の議論が政府、国会において更に進んでいましたら、こうした平成十五年以降の四回も勧告を受けることにはならなかったと承知しております。
本村伸子
この勧告は、女性差別撤廃委員会の委員に対して、日本の女性たちが多くずっと選択的夫婦別姓を求めて声を上げ続け、委員にも声を届け続け、そして四回も出ている、そういう重い重いものなのだということを是非皆さんにも知っていただき、選択的夫婦別姓を是非実現していただきたいということを強く強く求めたいというふうに思います。
六月十一日の日本維新の会の提案者の答弁の中で、選択的夫婦別姓二案に対して、子の氏について二つのファミリーネームを残せない旨の答弁がありましたけれども、何か方策があるのかという点もお伺いをしたいと思います。立憲民主党さんと国民民主党さん、お願いします。
西村委員長
米山さん、時間が来ますので、簡潔にお願いします。
米山議員
これに関しましては、そのままであれば原則としては確かに子供の氏は一つになりますけれども、なので、二つの両方を残すことはできませんが、しかし、改正後の民法七百九十一条一項の規定により、別氏の夫婦の子は家庭裁判所の許可を得ればその氏を父母の他の一方の氏に変更することが可能であり、その場合は兄弟姉妹の氏が異なってもいいことになります。
したがって、家庭裁判所の許可の要件はありますが、子の氏の変更の仕組みを使えば、別氏夫婦のそれぞれの氏を次の世代に残すことが可能です。
鳩山(紀)議員
基本的に立憲案と同じでございます。
西村委員長
本村さん、時間ですので、終わってください。
本村伸子
どうもありがとうございました。
これで終わらせていただきます。