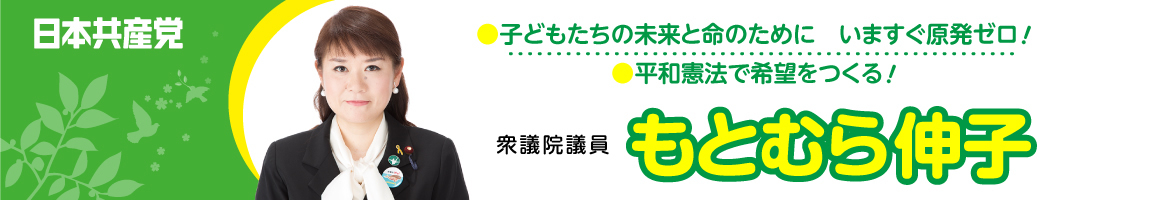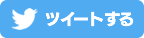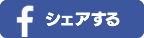質問の映像へのリンク
議事録
本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓は、個人を尊重する、個人の尊厳を大事にする、そういう家族をつくろうという積極的なものだというふうに思います。
個人の尊厳は家族解体に行き着くというような御主張もあるようですけれども、そのことに関して、選択的夫婦別姓は家族を解体するものではないというふうに当然ながら思いますけれども、井田さん、割田さん、寺原さん、志牟田さんに伺いたいと思います。
井田参考人
家族解体というか、家族にならせてほしい、法的に守られた保障のある家族でいさせてほしい、しかも同じ戸籍に載るようにしてほしい、そのように言っているわけなので、個人籍のお話が先ほどありましたけれども、全く当たらないですし、いつでもどこでも親族の身分関係を証明できるように、いつでもどこでもできるようにしてほしい、そういうことを言っているわけです。なので、全く当たらないと思います。
ありがとうございます。
割田参考人
私は、家族解体になるかもという話が、済みません、ちょっとよく理解できていません。
私は、名字が違っても家族と思って一緒に生きていきたいなというふうに思っております。
寺原参考人
ありがとうございます。
もし本当に家族を解体しようと思っているのであれば、戸籍制度とか婚姻制度というものにこだわらずに、個人で生きていく、あるいは、自ら事実婚を選んで生きていくという方々もいらっしゃると思います。
ただ、今ここで議論しているのはそうではなくて、今、家族として暮らしている実態がある、その実態がある方々をきちんと戸籍上も家族にして、戸籍上明らかにしてというものですので、私は、戸籍の根幹である、親族とか家族の身分関係を戸籍できちんと公証して検索できるようにするというその本質的な機能、それに逆に資するのじゃないかというふうに考えております。
志牟田参考人
御質問ありがとうございます。
そもそも、私は事実婚をしていてそんな家族の解体とか思ったことはなく、逆に、行政で、そうしないと家族でいられないという、要するに法律婚を認めない、夫婦別姓だったら法律婚を認めないという現状が家族を解体しているのではないかと思います。
本村伸子
ありがとうございます。そのことを確認させていただきました。
次に、井田さんに伺いたいというふうに思います。
国連の女性差別撤廃委員会でも旧姓使用に関する議論があったというふうに思うんですけれども、なかったという誤解もあるようですけれども、実際に日本審査の現場に行かれた井田さんに実際のところを伺いたいというふうに思っております。
井田参考人
御質問ありがとうございます。
国連女性差別撤廃条約では旧姓使用の議論はなされなかったからちゃんとやるべきだったというような御意見があったんですが、これは大きな誤りです。
私たち、二〇二四年十月、ジュネーブに赴きまして、日本審査にNGOとして参加をいたしました。旧姓使用の実態について、私たちNGOも委員に報告しましたし、日本政府代表団も、旧姓使用の拡大で、こういったこと、こういったこと、こういったことをやっていますと、不便、不利益を緩和していることというような主張を挙げて説明をしていましたが、結果、委員会からは、日本政府は民法七百五十条の改正のために何一つやってこなかったという勧告が、四度目の勧告を受けました。つまり、旧姓使用の拡大は何の措置も取ってこなかったと一蹴されたわけですよね。
日本審査のタスクフォースの責任者だったバンダナ・ラナCEDAWの委員はNHKに答えまして、女性の選択の問題、アイデンティティーの問題だ、日本は言い訳をやめるときだ、民意は明らかだ、もし日本が今の力やグローバルにおけるイメージを維持したいなら変化は必要だと語っておられ、これが国際人権条約に照らした日本政府の対応への評価ですということになります。
ありがとうございます。
本村伸子
ありがとうございます。その指摘も重く受け止めなければいけないというふうに思っております。
続きまして、割田さんに伺いたいというふうに思っております。
選択的夫婦別姓はいつか実現すればいい問題なのかという点です。今大事なこの瞬間の人生の選択肢を、選択をさせてほしいという思いを別の方からも伺っているんですけれども、「あすには」さんのホームページに載っているんですけれども、割田さんのお気持ちを是非お聞かせいただきたいと思います。
割田参考人
御質問ありがとうございます。
私は、すぐにこの選択的夫婦別姓を実現してほしいと思っております。
私は事実婚をしてからまだ半年です。その中で、事実婚を、もう長く事実婚の状態でおられる方々の話とかを聞いて、不安な気持ちになっています。今実現しないとすれば、そういった今のこのもやもや、この不安を抱えたまま時間を過ごしてしまうというのは、非常に、ちょっと心苦しいという気持ちですので、すぐに実現してほしいなというふうに思っております。
本村伸子
ありがとうございます。本当に、私たちがその言葉を国会議員として重く受け止めて、今すぐ実現しなければいけないというふうに思っております。
次に、寺原さんに伺いたいというふうに思います。
資料の中で、子の氏について、自由権規約、子どもの権利条約、最高裁の二人の裁判官の資料もつけていただいたんですけれども、そのことについて、恐らく時間がなかったのだろうというふうに思うんですけれども、お話をいただけたらと思っております。
寺原参考人
先ほど、子どもの権利条約についてお答えをさせていただいたので、そちらで大丈夫かと思います。ありがとうございます。
本村伸子
志牟田さんに伺いたいというふうに思います。
先ほど資料でいただきました資料の十六のところなんですけれども、選択的夫婦別姓制度について、二十五歳から三十四歳の女性では約九割が賛成、男性では六十五歳以上では七割超が賛成ということで、男性が年齢が上がれば上がるほど賛成が増えているというのは少し一般社会の世論調査とは違う結果になっているのではないかというふうに思いますけれども、そこの点についてコメントをいただければというふうに思っております。
志牟田参考人
御質問ありがとうございます。
このデータというかこの解析は、五月三十日まで回答者の回答を集めて、それで急いで解析した、本当に基本的な解析なので、どうしてかというのは私の臆測になってしまうんですけれども、恐らくこの年代というのは、管理職の年代になると思います。その管理職の男性が、そういった通称使用の女性が増えている現実を見て、これは変えぬといかぬじゃないのかなというふうに思っているんじゃないかと良心的に考えております。
本村伸子
現実を見てそういうふうに思われているということは、大事なことだというふうに思っております。
では、再び寺原さんに伺いたいと思います。
夫婦同氏制度に例外を許さないことの合理性について、訴訟の中で国から主張をされたことがあるのかという点、伺いたいと思います。
寺原参考人
ありがとうございます。
本委員会の中でも、何度か、最高裁が、夫婦が同氏である、一つにするということに合理性があるということで、そういうふうに家族が定義をされたんだというふうな御発言が何回かあったかと思います。
それは間違いで、最高裁は、一つに定めることにも合理性があるし、わざわざ別のところで、選択的夫婦別氏制度に合理性がないと言うことはできないということを明示しています。実際、家族の形が様々である中で、一つの形に決めるということは、なかなか最高裁の方で言うことはできないということかなというふうに理解をしております。
本村伸子
ありがとうございます。
また割田さんに伺いたいというふうに思います。
事実婚で、様々な法的な保護が受けられない、不利益があるということですけれども、公正証書を作ったということですけれども、これはどのようなときに生かせるのかという点、伺いたいというふうに思います。そして、その使い勝手といいますか、是非お聞かせをいただきたいと思います。
割田参考人
公正証書をどういうときに使うかという点ですけれども、正直、作ってからの半年間、どこかに公正証書を持っていって、結婚していますということを言ったことはありません。やはり、作っていく過程で弁護士さんにも言われたとおり、二人だけの約束にすぎないということが、実感したというところです。
公正証書の意義としては、私たちがいわゆる婚姻届のようなものを作りたいと思って提出したものですので、作ったことに関しては非常に満足感がいっていますが、あくまでも私たちのものだなという実感があります。
以上です。
本村伸子
ありがとうございます。
いま一度、寺原さんに伺いたいというふうに思います。
国連の女性差別撤廃委員会でも、社会的圧力によって女性が多く改姓させられているという指摘がございます。これは平等に選んでいるのかという声がありますけれども、どのようにお感じになるか、伺いたいと思います。
寺原参考人
ありがとうございます。
もちろん、夫婦間できちんと話し合って、自由かつ平等にどちらの氏にするかを決めているという夫婦はもちろんいらっしゃると思います。ただ、残念ながら、それが多い、多くのケースがそうであるというふうには言えません。
このフリップを見ていただけますと、これは昨年十二月の調査なんですけれども、どちらが改姓するかを実際に話し合ったかどうかということで、話し合った夫婦は一七%にすぎない。話合いを行っていない夫婦は七八%。特に、妻が改姓したケースで見ると、八割が話合いを行っていないということが分かっています。
話し合うまでもなく、夫婦の意思が合致しているということはもちろんあり得るわけですけれども、九五%の夫婦で女性が改姓しているという実態には、先ほど申し上げましたように、男女間の社会的、経済的格差だとか、婚姻したら女性が改姓するのが当然であるという男女不平等な価値観、慣習というものが作用しているということは否定できないかというふうに思っています。
別氏制度を導入することで、男女不平等な慣習の下でやむを得ず改姓をさせられるという女性が少しでも減るということになるんじゃないかなというふうに期待をしております。
本村伸子
ありがとうございます。
そうしますと、女性差別撤廃条約の中で、自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利などもありますけれども、やはり完全な合意というふうには言えないのではないかというふうに考えますけれども、その点、いかがでしょうか、寺原参考人。
寺原参考人
ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、本来であれば、当事者が二人で生きていくという、婚姻をして生きていくというその真摯な合意があれば婚姻ができてしかるべき、それが二十四条一項の婚姻の自由なわけですけれども、現在はそこに、婚姻の本質ではない、同氏にしなければいけないという要件が重なってきているということになります。
最高裁の判決ないし決定でも、違憲意見をおっしゃっている裁判官の方々は、自由かつ平等な協議がなされているとは言えない、自由かつ平等な意思で決めているとは言えないというふうに指摘をされているところです。
本村伸子
済みません、最後に、ジェンダーギャップ指数百十八位という問題について井田さんに伺いたいというふうに思います。
井田参考人
ジェンダーギャップ指数は、百四十八か国中百十八位という結果に今回なったということが数日前に報道されました。二〇二五年に三割のリーダー層を女性にというような呼びかけだけは勇ましいんですけれども、望まない改姓をした人たちにとっては確実にやはり家庭生活、業務上の足かせとなっているこの改姓の問題、改善がいまだされず、更に闘わねばならない。
役員層の方々ですと、例えば自分の法人の登記、役員登記もそうですね、特許や投資といった場面で、女性活躍というんだったら選択的夫婦別姓は必要でしょうということで、ビジネスリーダーの方々も非常に多く私たちの署名に声を上げていただいて、昨年、千人を超える役員以上の方々がサインした署名を国に出しました。
特に管理職における女性の割合というのが、百二十七位と非常に低かったんですよね。これは、先ほど女性も男性と同じく自分の氏名をフルスペックで名のる権利を取り戻す法改正だというふうに申し上げたんですけれども、やはり無駄コストが省けます。
あとは、政治分野でも、衆議院が一六%ぐらいの女性比率ということで、官僚の少なさも指摘をされました。これも、何の届けも不要で、自分の氏名で当選証書を手にして、閣議書や外交文書や公用旅券に公私一貫した自分の氏名を使えるというなら、やはり障壁がより取り除けるのではないでしょうか。
ランキング三位のノルウェーが選択制を導入したのは六十一年前です、六十一年。日本でも、市川房枝さんたちが、婚姻改姓が必要な状況を改めてほしいと国会請願に取り組んだのは実に五十年前になるんですね。そのときに書かれていたことを見ても、今、私たちの状況と何ら変わっていないというような状況なのです。
なので、先ほど研究者の方々も、事例としては非常に多くお困りの方がいらっしゃるといいますし、日本から永住権を取って行くランキングで三位のカナダにおいては、二〇〇一年から二〇二一年までの間にカナダに定住した人たちの女性比率が大変高いのが日本だと。七六%が女性だと。CBCというカナダの公共放送が放映しているのは、女性差別が激しいので優秀な女性たちがカナダに来てくれる、ウェルカムだというような記事だったわけですね。
こういう流出が既に始まっているということを、優秀層からやはり取られていっているということを、やはり国会議員の皆さんも、この氏の問題を一つのきっかけとして、本当に平等に、本当に自分が自分でいられるという権利さえ阻害せずに業務上も社会生活も送れているのかと問い直していただきたいなと思います。
以上です。
西村委員長
本村さん、時間ですので。
本村伸子
貴重な御意見を本当にありがとうございました。