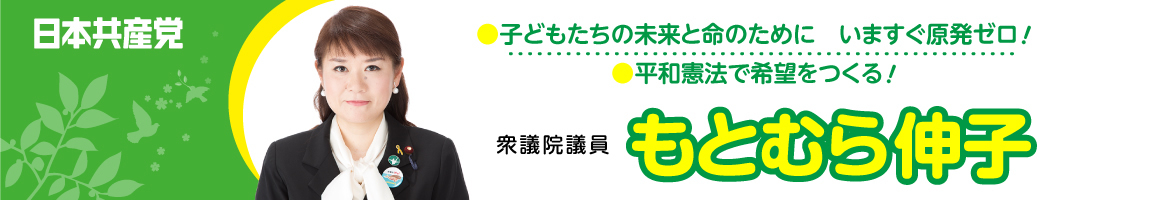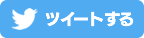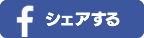質問の映像へのリンク
米農家や新規就農者への支援 国立病院内保育士処遇改善について 2025.6.10
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
農家の皆さんを本気で応援するべきだという観点から、質問をさせていただきたいと思います。
まず、伊東大臣にお伺いをいたします。農林水産業の振興は地域活性化にとって不可欠だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○伊東国務大臣
本村先生の御質問にお答えいたします。
まさに今おっしゃられたとおりでありまして、農林水産業の振興、まさに我が国の基幹産業であります。大事にしなければならないと考えております。
○本村伸子
ちょうど私、大臣のお地元の牛乳も飲ませていただいておりますけれども、本当に農家の皆さんを応援していくということがこの国にとって最重要のことだというふうに痛感をしております。
お米の農家は、二〇〇〇年以降、百七十五万戸から五十三万戸へ激減をしております。お米を作っても時給百円未満、二年連続時給十円という年もあったわけですけれども、これでは続けていくことができません。そして、子供さんに継いでいただくということもできません。お米の値段が今上がっておりますけれども、その根本的な原因は需要よりも生産量が下回っている現実がありまして、生産量を増やしていくためにも、お米作りに希望が持てるようにすることが必要であり、農家の皆さんへの価格保障、所得補償が必要だというふうに思っております。
そして、潜在的な需要というのはたくさんあるというふうに思うんです。昨日も私は愛知県内のお母さんから、食べ盛りの中学生がいて毎月十キロのお米を四人家族で買っていたけれども物価の高騰で七キロしか買えなくなってしまった、家計が大変で子供のための教材も先月切った、お米の代わりに百三十五円の五枚の食パンを朝食にして、でも一人一枚では足りない、塩むすびが食べたいと子供さんが言うのでお母さんが我慢をして子供さんに食べさせている、でも家計は三万円から四万円ぐらい毎月赤字だというお話をお伺いいたしました。
このように、潜在的な需要というのは、しんぐるまざあず・ふぉーらむの皆さんの調査でも、お米が買えなかった、よくあったというのが四五%、時々あった四三%、八八%のシングルマザーの御家庭がお米を買えないという現実があります。
主食であるお米をおなかいっぱい食べてもらうことを保障すること、そしてお手頃な値段で購入することができること、そして農家の皆さんも安心というためには所得補償、価格保障を実現することが必要だ、このことを同時にすることが必要だというふうに考えますけれども、笹川農水副大臣、是非お答えをいただきたいと思います。
伊東大臣、御退席いただいても構いませんので、ありがとうございます。御用事があるということで、大丈夫でございます。
副大臣、お願いしたいと思います。
○笹川副大臣
御質問ありがとうございました。基本的な考え方は、私も本村さんと一にしているというふうに思っております。
今回、米価の高騰に対して、遅々としてその効果が出なかったということについては、改めておわびを申し上げたいと思っております。また、今御党からも御提案がありますし、他の各党各会派からもいろいろな御提案がございます。
今年度、水田政策についてはしっかりと議論を深めていき、そしてまた、いわゆる九年度の予算編成に向けて要求をしていくということでありますので、御党からの御指摘についても真摯に受け止めたいというふうに思っております。
○本村伸子
ありがとうございます。
同時に、価格保障、所得補償、これもしっかりとやっていただかなければなりません。
それと同時に、新規就農者についても増やさなければなりません。四十九歳以下の新規就農者は、二〇一五年、約二万三千人だったものが、二〇二三年には約一万五千九百人というふうに激減をしております。これでは食料自給率を上げることが、本当に二十年、三十年先できるのかということになります。安全な食料をこの日本の大地で生産していくということは、安全保障上も非常に重要だというふうに思っております。
愛知県内のJAの方から、食料、胃袋を握られてしまって、不利な外交交渉をされた場合にのまなければならなくなるようなことでは駄目なんだと。国の主権を守っていくためにも、食料の自給率を上げなければならないというふうに思っております。
新規就農者が使える経営開始資金についてなんですけれども、経営開始五年後までに農業で生計が成り立つ計画を求めているのに、その資金は最長で三年しかない、厳し過ぎるということで、これは三重県の新規就農者の方からお話をいただきました。三年というのを、改悪してしまったのは二〇二二年のことだったというふうにお聞きをしております、最長五年に戻すべきだというふうに思います。
また、物価高騰の下で、資金というのは月々十二万五千円なんですね、二〇一二年から変わっていない。年間百五十万円ですけれども、これでは余りにも低過ぎるというふうに思います。二倍化を含めて増額をやるべきだというふうに思いますけれども、これも笹川副大臣にお願いしたいと思います。
○笹川副大臣
今委員が御指摘をいただきました見直しは、令和四年度に見直しを行いました。そのときに五年から三年と。ただ、併せて経営発展のための機械と施設等の導入というものを、都道府県と連携した支援を創設させていただきました。
あと、六年の補正予算においては、経営を継承する際に必要となる機械、施設の修繕や老朽設備の撤去などを支援対象に追加し、国の補助上限を引き上げた、五百万から六百万。これは、親元就農についても同様ということでさせていただきましたので、令和四年の見直しということで、また、令和六年度の補正予算ということでありますので、その執行状況を見ながらというふうに、確認はしなければいけないというふうに思います。
○本村伸子
設備投資しないともらえない、しかも借金が残るリスクがあるわけで、機械とか施設とかに投資する、そのことに支援を充実させていただくというのは非常に重要だというふうに思いますけれども、同時に、所得を補償するような資金を、三年から五年にまた元に戻していただくということと、月々十二万五千円ということも余りにも低過ぎるので増額を強く求めたいというふうに思います。
続きまして、国立病院の院内保育所の役割をどのように考えているかという点もお伺いをしたいというふうに思います。
また、院内保育所で働く保育士の皆様の処遇が著しく低いわけです。全医労の皆様のアンケート結果では、院内保育所で働く正社員、契約社員の保育士の基本給の平均は約十九万円です。月々二十万円もないんです。一般の保育士さんと比べても八万一千円低く、全産業と比べても十二万八千円低い。
このような状況をどのようにつかみ、改善していく計画なのか。今度は厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。
○仁木副大臣
本村委員の御質問にお答えします。
まず、国立病院機構の各病院におきます医療従事者の適切な勤務環境の確保を図る上で、院内保育所の果たす役割は大きいというふうに考えております。
国立病院機構内での院内保育につきましては、各病院が外部業者への運営委託契約により運営しているところでありまして、委託業者の保育士の処遇を含め、入札参加業者の業務内容等を適切に評価するとともに、委託業者やその雇用職員、保護者等と年に数回開催される会議等において話合いを行う等といった取組を行っていると聞いております。
厚生労働省といたしましては、国立病院機構が引き続きその責務を果たせるよう、今後の対応状況を注視してまいりたいと考えております。
○本村伸子
今のお話ですと、余りよく見えてこないわけです。
昨年の六月五日、衆議院の厚生労働委員会で宮本徹議員が、地域医療介護総合確保基金による補助の基準額、保育士一人当たり月補助単価が十八万八百円、これを引き上げるように求める質問をいたしました。
これに対して厚生労働大臣は、実態をちゃんと把握しようということは、きちんと私から指示を出しております、その結果として、もし極めて低い実態が確認されたということになれば、それを是正するための対応策は当然、その結果として検討していくことになるだろうと思いますというふうに答弁をいただきました。答弁の実態把握の結果をお示しいただきたいと思います。
また、一般の保育士の皆さんでいいますと、処遇改善は、二〇二四年度―二〇二五年度は一〇・七%となっております。物価高騰は一層深刻になっておりまして、院内保育所の社会的な重要性からしても、院内保育所の保育士の皆さんに早急に大幅な賃上げができるようにするべきだというふうに考えますけれども、副大臣の御見解を伺いたいと思います。
○仁木副大臣
まず、本村委員の御質問の趣旨はよく把握しておりますし、重要なことだと思っております。その上で、先ほど質問の中で述べられました宮本委員の質問の方も認識しております。
看護職員を始めとする医療従事者の離職防止や再就職を促進するために、子育てをしながら働けるような取組としまして院内保育所の設置は重要であると認識しておりまして、具体的には地域医療介護総合確保基金により支援を行っているところでございます。
御指摘のその院内保育所運営事業の補助基準額については、各都道府県が地域の実情に応じて設定することが可能となっており、国が一律の基準を定めているものではないわけでございますが、先ほどの御質問を受けて各都道府県の交付要綱等を確認しました。当該補助基準額については、多くの都道府県が平成二十八年度に示した補助事業例に記載の金額を参考としておりまして、一部の都道府県においては、その中でも、県の判断で標準事業例に記載の金額よりも高い金額を設定するといった対応を行っている状況であることが分かりました。
繰り返しになりますが、補助基準額については各都道府県が地域の実情に応じて設定することが可能となっておりますので、現下のこのインフレの中での状況での本村委員の指摘を踏まえまして、引き続き、各都道府県において実情に応じた適切な基準額の設定がなされるよう、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○本村伸子
答弁の実態把握の結果の部分なんですけれども、もう少し細かくお示しをいただけないでしょうか、厚生労働省。都道府県のうち、幾つがとか。
○谷委員長
厚生労働省は、参考人は来ていないですね。
○本村伸子
来ていないということですので、後でお示しをいただきたいというふうに思います。
必要な対応をしていくんだ、それは賃上げをしていくためにということでよろしいですね。
○仁木副大臣
現在の財政当局との調整はどうかということもありますけれども、鋭意今協議中です。具体的な見通しは、今、幾ら、どうこうという、詳細に関しましては申し上げられませんが、改善を目指しての協議であるというふうに認識しております。
○本村伸子
国立病院の医師や看護師の皆さんからもお話をお伺いする機会があるんですけれども、本当に人がいなくて現場は泣いているような状況です。そして、家族を犠牲にして、本当に一生懸命頑張ってくださっております。
人を確保するためにも、院内保育所、保育士さんの存在というのは本当になくてはならない状況です。看護職員の方々、夜勤なんかもしていただいて、なかなか子供さんとも十分会えない現実もあるわけで、せめて身近なところで保育をしていただいて少しでも子供と触れ合える時間を確保していただくということも含めて、是非応援をするためにも充実して保育士さんの処遇改善をしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。