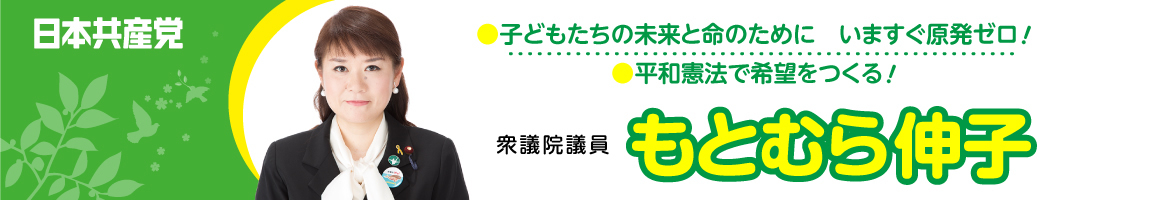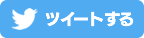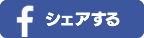質問の映像へのリンク
JP ナビゲーションをスキップ 本村氏「保育の質後退も」 児童福祉法等改定法案が可決 作成 アバターの画像 保育の質の確保と児童虐待対応について 2025.4.3
議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今回の法案、保育士不足に対処するというものと言われておりますけれども、やはり根本的なところに手を打つべきだというふうに考えております。
保育士不足に関しては、ほかの産業と比べても低い賃金を引き上げるということ、そして子供の命と安全、発達を保障する、そして人権を保障する、保育士の皆さんにそういうことを保障して、やりたい保育がちゃんと実現できるようにしていくこと、そのためにも保育士の配置基準の改善ということが必要ですし、保育士さんが産休や育休を取るときに、本当にごめんねと周りの方に言いながら、泣きながら取るような状況がありまして、そういう環境を変えていくこと、有休も、そして病休も取りやすくしていくということ、こうしたことこそ保育士不足の解消の道だというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○三原国務大臣
今もお答えさせていただいたとおり、保育士の皆様の処遇改善、そしてまた配置改善ということは大変重要なことだというふうに思っております。
このため、処遇改善につきましては、私が大臣になって本当に最初の予算であります令和六年度の補正予算からしっかりと一〇・七%という大幅な改善を実施しようということで、これは令和七年度予算でも財源を確保した上で反映させていただいたところであります。そして、今まさにお話しさせていただいた、昨年の十二月に公表いたしました保育政策の新たな方向性で、他職種と遜色ない処遇の実現、こうしたものを掲げさせていただいたところであります。
やはり処遇改善、お給料の面、先ほどもお話ししましたけれども、それだけではなくて、やはり働きやすい職場環境ということが、委員御指摘のとおり、大変重要だというふうに考えております。現場へのICTの導入ですとか、また保育補助者の配置の支援、こうしたことも環境づくりに取り組むためには大変重要なことだというふうにも思います。
そうした意味も込めて、今回の法案で保育士・保育所支援センターというものを法定化して、保育士の就労環境向上のための相談支援等の業務を行う体制の整備を行っていくということ、これもまた大変重要なことだと思っておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○本村伸子
補正予算と今年度の予算の中で処遇改善ということで一〇・七%ということですけれども、例えば大臣のお地元の神奈川県の方からお話をお伺いしたら、やはり保育園としては基準を超えて加配しているわけですよね、子供たちのために。なので、そういう方々の給料も保障しないといけないということで、そのことを合わせると、現場では半分ぐらいになってしまうんじゃないかというお声も聞いております。
そして、保育士の皆様や保護者の皆様から切望されてきた一歳児の保育士の配置基準の改善が、今年度、見送られてしまいました。保育現場からは落胆と憤りの声が寄せられております。
加算の予算は増えましたけれども、結局のところ、要件があって、実際に一歳児のところの保育士を加配している保育園でも加算が取れないという実態があります。現場の皆さんを失望させているというふうに思うんです。
こども家庭庁の一歳児の加算を取る要件は、私は本当に子供さんのことを第一に考えた要件なのだろうかというふうに疑問を持つ点がございます。
一つは、職員の方々の平均経験年数が十年以上の保育園は加算の一つのハードルを越えることができるというふうになっているんですけれども、十年未満の保育士さん、ベテランの方々が少ない保育園、だからこそ子供たちのために保育士の配置を手厚くするというのが必要なのじゃないかというふうに現場からは言われております。
また、デジタルの保育計画、これもポイントが一つクリアできるわけですけれども、デジタルか手書きかなのではなく、例えばデジタルでも、コピー・アンド・ペーストした保育計画だったらその子のためにならないわけですよ。やはりその子のための保育計画であるかどうか、この点を評価するべきだというふうに思います。また、デジタル導入ということで、導入費やメンテのお金も必要だというところも、ハードルが現場にはあるわけです。
いろいろな要件をつけて実際に一歳児のために保育士が加配されているのに、その要件のために一歳児の加算が取れないという現実があります。一歳児の加算が取れないと、一歳児さんのための加配された保育士は公定価格の給料のアップの対象外になってしまうわけです。そういうふうになるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○三原国務大臣
保育士等の処遇改善について、先ほどお話をさせていただいたとおりでありますが、公定価格について、園児の人数に対する保育士の人数を決めた法令上の基準である配置基準や、公定価格上、評価することとしている加算分、これを基に算出しておりますので、保育の現場においてこうした配置基準や加算分を超える保育士が配置されている場合には、機械的な計算どおりにならない場合があるということは承知しております。
他方、今般の当初予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、通常の教育、保育に従事する全ての職員を対象とすることを可能としておりまして、各事業者においてその実情に応じながら処遇改善を進めていただきたいというふうに考えているところでございます。
○本村伸子
入ってくるお金は公定価格のところということで、それをどのくらいの人に分配するかという話で、一人一人が薄くなってしまうわけです。
私は、以前に、一歳児の子供さんの命が失われてしまった事故が相次いでいるということ、そして、自治体のその事故の第三者の検証の報告の中で、配置基準の改善が必要なのだというふうに書かれていることを指摘いたしました。
一歳児の保育士の配置基準を改善するべきだというふうに思います。また、少なくとも一歳児の保育士の加配を実際に行っているところに対しては加算を使えるようにするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○三原国務大臣
先ほども申し上げましたように、御指摘の一歳児の配置改善は、三歳児や四、五歳児の配置改善より大変多くの保育人材が必要となるため、まずは、基準の見直しではなくて、保育の質の向上、職場環境、処遇改善等の観点から、一定の要件を満たす事業所への加算措置による対応を進めるものでございます。
いずれにしても、一歳児の配置改善、これは五十数年ぶりであります。まずはこの形で、令和七年度から一歳児の配置改善加算、これを着実に実施して、そして保育現場における職員配置の改善を進めていく、その上で、本要件の在り方につきましては、加算の取得や実際の配置の状況等を踏まえて、また検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○本村伸子
実際に子供たちのために加配しているわけです。五人に対して一人ですとか、四人に対して一人、こういう保育園がある中で、その要件があるために国からはお金が入らないというところは市町村が配るわけですけれども、それは直ちに改善していただきたいというふうに思っております。
子供たちのことを真ん中にして考えているのかという問題、もう一つございます。幾つもあるんですけれども、小規模保育についてです。
今回は全国で三歳以上の子供さんの小規模保育ができる規定になっているんですけれども、小規模保育についてはA型、B型、C型というものがありまして、ビルの一角というところもあり、もちろん一生懸命やっているところもあるということを私もお話を聞いて存じ上げておりますけれども、三歳児以上の子供が過ごす、そういう場として本当にふさわしいのかということもございます。
A型は保育士さんで保育してくださいと。しかし、営利法人が五三・七%、そして人件費割合が六四・八%ということで、通常の認可保育園でいいますと、人件費というのは七五・一%なんですけれども、A型の人件費は六四・八%。B型になりますと、保育士は二分の一以上でいいですよということになっておりまして、営利法人の割合は四七・四%、人件費の割合は六四・五%。C型となりますと、保育士でなくてもいいですよ、研修を修了した人でいいですよというふうになっておりまして、営利法人の割合は三五・二%、人件費割合は六二・五%というふうになっております。特にB、Cは、国家資格である保育士ではない方々が見ているという点で、保育の質に格差ができてしまうのではないかという懸念もしております。
今回の法案は、三歳以上のみ小規模保育ということで、A型を想定しているんですけれども、でも、そのことは法律に書いていないわけです。ですから、将来、B型、C型に拡大するんじゃないかという懸念もありますし、地域の皆さんにお伺いをしたら、今、公立保育園を潰す動きがあるんですけれども、質の向上のためにも大切な役割を果たしている公立保育園を潰して、そちらの保育に、受皿としてこの小規模保育が使われてしまうのではないかという懸念の声も出されております。
やはり、保育の質を低下させる、そういう施策ではなくて、保育環境を整えて、保育士を手厚く配置して、子供たち一人一人の命と安全を守り、そして発達を保障する、そういう施策こそ、今、求められていると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○三原国務大臣
小規模保育事業所における保育の質の確保は重要であると考えておりまして、特に三歳から五歳児の保育、〇―二歳児と比べて教育的な要素が強く、専門性を持つ保育士による関わりが重要であるということを踏まえ、今回の改正におきましては、保育士のみを配置するA型に限って全国展開することとしております。
この小規模保育事業のA型、B型、C型の類型、これは従前より内閣府令で規定されているものでございまして、今回の三から五歳児のみの小規模保育の創設におきましても、これは、法律ではなく、内閣府令で対応することとしております。
なお、B型及びC型については、令和六年十二月の国家戦略特別区域諮問会議決定において、引き続き特区での実証や活用ニーズ等を踏まえて全国展開の可否を検討するとされて、引き続き、特区の仕組みの中で実施し、検討することとしており、今回の法改正の議論の中でいただいた保育の質を担保すべきという趣旨の御意見等も踏まえまして、関係者の御意見も伺いながら、丁寧な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
○本村伸子
保育の質がやはり後退するのではないかという懸念があります。法律事項ではないために、やはり白紙委任はすることはできないというふうに思っております。
認可保育所と比べても人件費比率が低いということで、処遇の水準が低くなってしまうという懸念もございます。こうした問題もございます。
また、一時保育の子供さんと保護者の面会に関しては、パートナー弁護士なんかも配置して、子供の権利を保障できるようにすることと同時に、臨床現場では、家庭裁判所で面会交流を決められた子供たちが、面会交流を嫌悪し、面会をめぐる別居している親との紛争にさらされ、あるいは、過去のトラウマから回復が進まず、全身で苦痛を訴え、不適応を起こして健康な発達を害している事例が増えているという学会の指摘もございます。
こうしたこともしっかりと、一般社団法人日本乳幼児精神保健学会の皆さんが声明を出しておりますので、こうしたことも踏まえて、丁寧に、慎重に運用していただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
○本村伸子
私は、日本共産党を代表し、児童福祉法等の一部を改定する法律案に反対の討論をいたします。
反対の理由の第一は、保育の質を後退させる危険性があるからです。
小規模保育事業は、待機児童対策として、原則ゼロ歳児から二歳児を受け入れてきました。本改定案は、三歳児以上の子の受入れを可能とするものです。小規模保育事業は、マンションなどの一室が使われることもありますが、活発に動く三歳以上の子供の活動を制限し、小さな部屋で保育することは、現行の保育所の認可基準から後退させるものであり、認めることはできません。公的保育の質の向上のために必要な公立保育園が廃止され、その受皿になるのではないかとの懸念の声も出されています。
また、小規模保育事業は約半数が営利法人が運営しており、市町村から支払われる運営費には使途制限がないため、保育士の人件費等、処遇低下のおそれがあります。
第二の理由は、公的保育の非営利原則を弱めることにつながるからです。
国家戦略特区における地域限定保育士の試験について、筆記試験は通常の試験と同じですが、都道府県で行われる講習会を修了した人は実技試験が免除されます。本改定案は、これを全国展開するものです。保育士不足の背景にある処遇や配置基準の問題を抜本的に改善せず、緩和策で保育をする人を確保しようとするものであり、認められません。保育士の抜本的な処遇改善と保育士配置基準の抜本的な改善によって、保育士確保を進めるべきです。
また、地域限定保育士の試験については、認定を受けた都道府県又は指定都市が行う判定事務の委託を営利企業にも認めるなど、公的保育の非営利原則を弱めるものであり、認められません。
なお、反対ではありませんが、本法案では、一時保護された子供と保護者との面会等制限について、行政処分として児童虐待が行われた場合に加えて、児童虐待を行った疑いがあると認められる場合にも可能としています。
保護者と子供の面会は、子供の意思の尊重が何より重視されなければなりません。子供の権利を擁護する子供パートナー弁護士などを位置づけること、DV、虐待ケースでは、DV、虐待の被害者支援の経験を有し、複雑な子供の心理を理解する高い専門性を持った児童精神科医や児童心理司などによる子供の意思の確認など、慎重に対応する必要があります。そのためにも、児童相談所の体制強化、児童福祉司、児童心理司など職員の定着化のプログラムが必要です。
以上を指摘し、反対討論といたします。