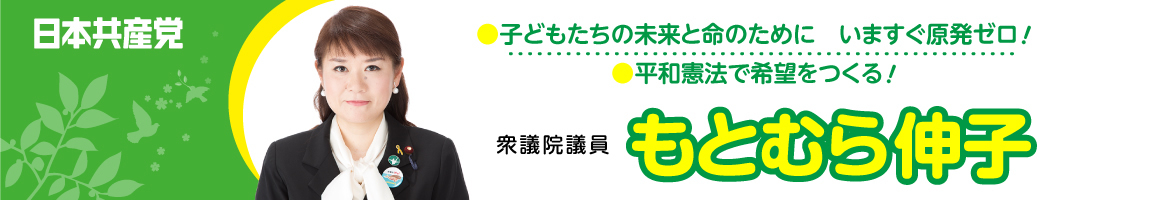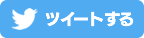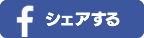質問の映像へのリンク
労災病院の交付金返納で経営悪化危機的事態 政府にただす 2025.2.28
議事録
〇本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
医療、介護、障害福祉のケア労働者の方々の賃上げについて質問させていただきたいというふうに思います。
まず最初に、二〇二四年の賃上げの実態を産業ごとに、金額と賃上げ率をお示しをいただきたいと思います。金融・保険業、建設業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、電気・ガス・熱供給・水道業と医療、福祉の分野、また、二〇二四年の民間主要企業の春季賃上げの妥結の賃上げの額と率をお示しをいただきたいと思います。
○森川政府参考人
お答えいたします。
令和六年賃金引上げ等実態に関する調査の結果によりますと、一人平均賃金の改定額及び改定率は、金融業、保険業は一万五千四百六十五円で四・六%、建設業は一万五千二百八十三円で四・三%、情報通信業は一万四千九百八十九円で四・三%、学術研究、専門・技術サービス業は一万四千七百七十二円で四・四%、電気・ガス・熱供給・水道業は一万四千六百十九円で四・三%、医療、福祉は六千八百七十六円で二・五%となってございます。
また、令和六年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況では、平均妥結額は一万七千四百十五円、賃上げ率は五・三三%となってございます。
○本村伸子
パネルにもさせていただいて、大臣もよく認識をしていただいているというふうに思うんですけれども、民間の主要企業でいいますと、賃上げ額は一万七千四百十五円、賃上げ率は五・三三。しかし、一方で、医療や福祉の分野は二・五%にとどまっている。医療、介護、障害福祉の賃上げは、全産業と比べても低く、置き去りになっているというふうに認識をしております。見劣りをする賃上げ額、賃上げ率になっております。
この現状について、大臣はどのように認識をされておられますでしょうか。
○福岡国務大臣
医療、介護、障害福祉分野におきましては、今、他産業との厳しい人材獲得競争にさらされておりまして、賃上げの実現というのは喫緊の課題だというふうに認識をしています。
こうした中、令和六年度報酬改定において必要な措置を講じるとともに、令和六年度補正予算においても更なる賃上げ等の支援を盛り込んだところでございまして、引き続き、政府全体として賃上げに向けた取組を進めていくことが大変重要だ考えております。
○本村伸子
補正予算も組んだというお話ですけれども、医療、介護、障害福祉、全ての労働者が賃上げできるかどうか、また、全産業並みに上がるかどうか、このことが問われているというふうに思います。
医療、福祉の分野は、女性が大変多く働いている現場です。ケア労働者の賃上げというのは、男女の賃金格差の是正にも必要なことで、そして有効だというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
○福岡国務大臣
男女間の賃金の差異につきましては、長期的には縮小傾向にございますが、まだ依然として差異は大きくございまして、その是正については大変重要な課題だと認識をしております。
このため、これまでも女性活躍推進法等に基づく取組を進めてきたところでございますが、今般、男女間賃金差異の情報公表の強化等を盛り込んだ女性活躍推進法の改正法案をこの国会に提出すべく、今準備を進めているところでございます。
委員御指摘がございましたように、女性が多く働く医療、福祉分野におきまして賃上げが行われることは、男女間の賃金格差の縮小にもつながり得るものであると考えています。
○本村伸子
その分野、医療、福祉の分野で、やはり賃上げ率、額が見劣りする現状であっては、格差は縮まらないということになってしまいます。
介護や障害福祉の分野、ほかの産業と比べても年収格差があるということで、全産業と比べて年収格差をなくしていくということが求められていると思いますけれども、その点についても大臣の御認識を伺いたいと思います。
○福岡国務大臣
介護職員、障害福祉関係職員の平均給与につきましては、全産業平均との差が、二〇〇八年時点では、介護職員が月額十・六万円、障害福祉関係職員が十・二万円でございましたが、これまでの累次の処遇改善の取組によりまして、二〇二三年時点では、介護職員が六・九万円、障害福祉職員が六・五万円に縮小してきております。ただ、縮小したとはいっても、依然として差がある状況だというふうに認識をしております。
介護、障害福祉分野における人手不足、大変厳しい状況であるということは認識してございまして、また、今年度の実績等を見ますと、賃上げに向けた取組は他産業が先行していると認識してございます。そのため、政府としては、これらの分野での処遇改善は喫緊の課題であると考えています。
○本村伸子
介護の分野でいいますと、格差がまた開いてしまっているという数値も出ておりますので、そのこともよく認識をしていただいて、全産業並みに、それ以上に賃金を上げていただきたいというふうに思っております。
介護、障害福祉の分野は元々、全産業と比べても賃上げ額、賃上げ率が最低となっております。そうしますと、ますます格差が拡大するということになってしまいます。医療も介護も障害福祉の分野も、本当に人手不足で深刻になっています。大幅な賃上げがどうしても必要だというふうに思います。
昨年十二月の補正予算で一定措置をしておりますが、医療、介護、障害福祉で働く皆さんの賃金の引上げが、二・五%の賃上げということが目標になっておりまして、二〇二五年は二%の賃上げが目標となっておりますけれども、補正予算でどのくらいまで引き上げるのか。そして、なぜ単年度だけなのだという問題があると思いますけれども、なぜ単年度なのか、その点もお答えをいただきたいと思います。大臣に通告していると思います。
○森光政府参考人
医療、介護、障害福祉分野は、他産業との厳しい人材獲得競争にさらされており、人材確保の課題に緊急的に対応する必要があると
いうことで、今般の補正予算で臨時的な措置を図るというものでございます。
医療分野においては、現場の更なる賃上げや業務効率化につながるよう、病院では一床当たり四万円、診療所、訪問看護ステーションでは一施設当たり十八万円を支給するものでございます。
介護、障害分野においても、更なる賃上げにつなげるものとして、介護職の配置があるサービスを対象に、積算上は、常勤換算の介護職員一人当たり五・四万円の支援を行うこととしております。
まずは、こうした措置を着実に実行し、医療、介護、障害福祉分野で働く方に必要な支援が行き届くよう取り組むとともに、今後、補正予算等の効果を丁寧に把握をした上で、適切に対応していきたいと考えております。
○本村伸子
その効果なんですけれども、例えば、医療従事者の方々の賃上げにも使えるということで、一床当たり四万円ということで示されておりますけれども、これは賃上げに優先的に使えるんでしょうか。
○森光政府参考人
議員御指摘の生産性向上・職場環境整備等支援事業というものでございますが、これは生産性向上や賃上げを図るものでございまして、ICT機器等の導入による業務の効率化、タスクシフト・シェアによる業務効率化、既に雇用している職員の賃金改善のいずれかの取組に医療機関の判断で活用が可能な支援となっております。
いずれにしましても、本事業を通じまして、現場の更なる賃上げや生産性向上につながることが重要であると考えておりまして、こうした措置を着実に実行し、必要な支援が医療機関に行き届くよう取り組んでまいりたいと考えております。
○本村伸子
ですから、これは必ずしも賃上げに使うと確実になっているわけではないわけです。そういう中で、二・五%の賃上げ目標、二%の賃上げ目標、これは補正予算でどのくらい、医療、介護、障害福祉、賃上げになるのかというふうにお考えになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
○森光政府参考人
先ほど答弁させていただきましたけれども、繰り返しになる部分がありますが、お許しいただきたいと思います。
この補正予算に関しては、臨時的な措置を図るというものでございますが、医療分野においては、現場の更なる賃上げ、業務効率化につながるよう、病院では一床当たり四万円、診療所、訪問看護ステーションでは一施設当たり十八万円を支給するものとなっております。医療機関においては様々な職種がございますので、どのような形になるかについては医療機関の判断となると思います。
また、介護、障害分野においても、更なる賃上げにつながるものとして、介護職の配置があるサービスを対象に、積算上、常勤換算の介護職員一人当たり五・四万円の支援を行うということにしております。
まずは、こうした措置を着実に実行してまいりたいというふうに考えております。
○本村伸子
それでも、やはり全産業と比べて見劣りがする状況だというふうに思います。
例えば、全国老人福祉施設協議会の皆様始め、介護関係の十二団体が、他産業への職員の流出を更に加速させる、基本報酬の引下げがあって、更にそうした流出を加速させてしまうという懸念の声も出ている中で、確実に賃上げが他産業と同じように、あるいはそれ以上に、エッセンシャルワーカーですから、それ以上にできるようにしていただきたいというふうに思うんです。
医療、介護、障害福祉の現場では、本当に悲鳴が上がっております。今日は、労災病院について具体的にお話をさせていただきたいと思うんですけれども、労災病院では、労働者健康安全機構が病院勘定から百七十三億円、交付金十億円を国に返納をした、二〇二四年度の収支計画についても百二十六億円の赤字となり、数年で資金が枯渇するというふうに機構が述べております。資料の二と三を見ていただきたいんですけれども、そこに機構の方が示した資料があるわけですけれども、そこに、二の資料を見ていただきますと、二〇二六年、資金が枯渇というふうに書かれております。そして、資料の三、一番下のところ、赤いところですけれども、本部管理資金を本年七月、これは二〇二四年七月のことですけれども、百七十三億円、国庫納付したこともあり、資金枯渇を見込む時期が早まっているというふうに書かれております。
今、一時金、ボーナスについて、大幅な減額の提案となっています。労災病院では離職が元々相次いでおりましたけれども、更に加速をしてしまうんじゃないか、また、老朽化しているのに建て
替えもできない病院もあるというふうに聞いております。
こうした労災病院の危機的な事態について、大臣はどのように把握をされておられますでしょうか。
○福岡国務大臣
私も先日、労災病院の関係の方とお会いして、直接お話を聞く機会がございました。
労災病院の収支は令和五年度から悪化し、今年度は、更にその状況が深刻化することが見込まれているというふうに承知をしております。
そのような中で、御指摘がございました、労災病院職員の賞与の見直しを行ったこと等についても報告を受けてございます。
労災病院の経営悪化を受けまして、病院を運営する独立行政法人労働者健康安全機構に対しまして、病床利用率の改善等による収入の増加や経費の節減など、収支改善に取り組むようお願いをしているところでございます。
なお、御指摘の国庫返納につきましては、令和五年度末の中期目標期間満了時の積立金の一部から、独立行政法人通則法等の規定に沿って行ったものでございます。また、病院システムの更新等、必要不可欠な経費につきましては、令和六年度補正予算においても、その必要不可欠な経費に限定して特例的に補助するといった対応を講じているところでございます。
労災病院につきましては、もう御承知のとおり、あくまでも診療報酬を基礎とした運営を行っていただくことが原則でありますため、引き続き収支改善に取り組んでいただけるよう、厚生労働省としても、その状況を注視するとともに、必要な助言等を行ってまいりたいと考えています。
○本村伸子
厚生労働省から収支改善などの助言をしたということですけれども、現場では、九十七億円、収支を改善する方針というふうに伺っております。そのうち三十億円は、入院患者などを増やすということで改善するというようなお話、そして六十七億円は、一時金の引下げということになっております。厚生労働省の助言の下で、一時金の引下げ、これで収支を改善するということを言われているようです。
一時金が減って、人が辞めたり、募集しても更に集まらなくなる、そうしたら、看護職員の方々がいなくて、ベッドの稼働率を上げることはできないということになってしまいます。これは経営状態も悪循環になってしまいます。こういうことは絶対に避けていただきたいというふうに思います。
この一時金の問題は、昨年の秋に四回、ストライキを労働組合の皆さんがされております。そして、一時金に関しまして、中央労働委員会へあっせんを求め、そして、一月下旬にあっせん案があったそうですけれども、今の段階では、一・六月というふうに前年よりも悪くなっているわけです。この月数というのは、国立病院機構ですとか、JCHOさんですとか、日赤さんよりも低い状況になっています。そして、二〇二五年夏の一時金は一・五か月ということで、夏と年末、四か月ないとほかの病院に移るというのが医療従事者の方々の動向だというふうに言われております。
命と健康を守るエッセンシャルワーカーでありながら、働く意欲を失い、離職に追い込まれるということが労災病院の中であってはならないというふうに思っております。
私の地元の愛知県ですけれども、中部労災病院さんは、名古屋市内で、例えばコロナのときに、感染症病床というのは大変少ない状況がありまして、ほかの自治体にある病院にも様々お願いをしてきた状況があるわけですけれども、ベッドが少ない中で亡くなった方々もおられるわけですけれども、そういう状況の中でも中部労災病院の皆さんは対応してくださいましたし、中部労災病院だけではなくて旭労災病院さんもそうですけれども、今後も対応してくださる、そして、何かあったときに医療従事者を派遣してくださるということで、愛知県とも協定を結んでくださっております。
地域にとっては本当になくてはならない病院で、そこの医療従事者の皆さんがいなくなってしまったら、本当に地域医療にとっても大損失になるわけです。そうやって頑張ってくださっている方々が、一時金が大幅に減らされてしまう、そして経営危機にある、これを放置をすることは絶対にあってはならないというふうに思っております。
労災病院でも全産業並みに賃金が引き上がることができるよう、働く人たちの悲鳴を聞き、そして状況把握をして支援をするべきだ。もっと支援を抜本的に、助言だけじゃなくて、財政的な支援をもっと抜本的に強化をするべきだというふうに思います。国庫返納のときの計算が、本当に見積りが正しかったのかという問題もあるというふうに思うんです。是非、その点も踏まえて支援を強めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○福岡国務大臣
まず、繰り返しになりますが、医療従事者の方々の処遇改善というのは大変重要な課題であると認識をしております。
御指摘のとおり、労災病院職員の所要の見直しを行ったということは事実でございますが、一方で、令和六年度診療報酬改定上の賃上げの仕組みを活用して、令和七年一月時点におきまして、前年同期比で約三・三%の平均月例賃金の引上げを行っているなど、厳しい経営状況にあっても、可能な限りの処遇改善に取り組んでおられるものと承知をしております。
また、繰り返しになりますが、病院システム更新等、必要不可欠な経費については、令和六年度補正予算において、その必要不可欠な経費に限定して特例的に補助するといった対応も講じております。
労災病院については、あくまで診療報酬を基礎とした運営を行っていただくことが原則でありまして、厚生労働省としては、引き続きその収支改善に取り組んでいただくようお願いするということでございますが、お話ありましたように、ほかの民間病院も、診療報酬を基礎とした運営をしていただいています。
病院経営は、あまねく全般的に今厳しい状況でありますから、先ほどおっしゃられましたように、地域医療を支えておられる病院がその地域で引き続き運営していただけるためにどういうことができるのかということについては、しっかり検討してまいりたいと思います。
○本村伸子
国庫に返納をして悪化をしている、もう資金が枯渇するという危機なんです。二〇二六年には枯渇するという危機なんです。
ですから、国庫に返納をしたというところが悪化を早めてしまったということがあるわけですから、そういう点も踏まえて更に支援を強めていただきたいということで、大臣、もう一度お願いしたいと思います。
○福岡国務大臣 まず、先ほど申し上げましたように、この国庫返納につきましては、独立行政法人通則法等の規定に沿って行ったものでございます。その上で、あくまでも病院経営については診療報酬を基礎とした運営を行っていただくことが原則でございますが、しっかりそこは収支改善に取り組んでいただけるよう、厚生労働省としても、その状況を注視するとともに、必要な助言を行ってまいりたいと考えています。
○本村分科員 必要な助言はもうして、それが一時金の削減になっているわけですから、そうじゃなくて、全産業並みに引き上げることができるように支援をお願いしたいと思います。
○福岡国務大臣 ですから、そこは先ほども申しました。労災病院ではなく、ほかのいろいろな医療機関も、診療報酬を基礎とした運営を今行っていただいているということでございます。そして、その中で、今、病院経営は全般的に厳しい状況の中で、病院経営の、どうやったら地域医療を維持していただけるか、そういった体系の中で考えていく必要があると思います。
○本村分科員 是非、支援を強めていただきたいというふうに思います。
ほかの病院でも、例えば国立病院機構や地域医療機能推進機構の病院でも、防衛財源として国庫返納で賃金、労働条件が悪化するという危機がございます。国立病院機構でも二〇三一年度には法人資金が枯渇するおそれがあるというふうにニュースに出ておりました。今日もストライキが行われるというふうに言われております。
医療現場をこうした状況に追いやっているのは政府の責任です。国の所管する機構等の病院でも全産業並みに賃上げができるようにするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○福岡国務大臣 独立行政法人の運営につきましては、法人の自主性を基本として行われるものでございまして、その賃金につきましては、法人の労使で真摯に協議いただいて適切に決定されることが重要だと考えております。
その上で、政府といたしましては、国立病院機構等を含む医療機関の更なる賃上げにつながるよう、昨年末に成立した補正予算におきまして、現場の更なる賃上げやICT機器等の導入による業務効率化を支援することとしてございまして、そうした必要な支援が行き届くように着実に取り組んでまいりたいと思います。
○本村分科員 是非、支援を強めていただきたいと思います。
大変な人手不足になっております。病院では人手が足りない。基本的な指針の処遇の改善の項には、夜勤の負担の軽減ということで、月八日以内、夜勤の体制を構築するというふうに書かれているのに、夜勤が九回、十回、十一回という現場もあります。そして、育児をしながら勤務をされている方が、育児短時間勤務というふうになっているのに短時間勤務ではない現場もあります。また、準夜勤も、育児短時間勤務の方もやらないといけないというような現状があります。
医療や介護、障害福祉、魅力ある職場にしていく、賃金も上がるし、そして人も増えていくというような、見通しが立つような、希望が見えるような、そうした、もう少し我慢すればよくなっていくんだというビジョンを是非示していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○福岡国務大臣 私も、この政治の世界へ入って二十年近くになります。その間ずっと、様々な医療機関であったり、介護、障害福祉の現場を拝見させていただいてまいりました。それぞれの場所において、日々のサービスの提供を支えていただいている従事者の方々の献身的な御努力について、これまでも拝見したところでございまして、心から敬意と感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
その一方で、委員御指摘ありましたように、今、限られた人材の中で、それぞれ、かなり業務負荷も重くなって、厳しい環境に置かれているということは十分承知をしております。
より魅力あるものとなるように、例えば、各都道府県に設置されました医療勤務環境改善支援センターによる助言等の支援であったり、また、IC等を活用した勤務環境の改善を推進するとともに、医療、介護従事者の賃上げを行うために、令和六年度報酬改定や、令和六年度補正予算において、更なる賃上げに向けた支援に着実に取り組むこととしております。
あわせて、人材確保の課題に対応しつつ、限られた人員で質の高いサービスを提供していく工夫も必要でありますことから、業務の効率化等により、業務負担の軽減を図りながら、生産性向上の取組を推進していくことも重要だというふうに考えています。
このような視点を重視しながら、医療、介護等が将来にわたって適切に提供できる環境を整えてまいりたいと考えています。
○本村分科員 二〇二五年の医療、介護、障害福祉の賃上げの目標は二%となっております。二〇二四年よりも低い目標となっています。これ自体が、私はおかしいのではないかというふうに思っております。全産業並みに、二〇二四年の遅れを挽回するためにも、全産業以上に賃上げを図る必要があるというふうに思っております。
そして、二月二十五日に石破総理が、医療、介護、障害福祉分野の生産性の向上を図るためのプランの策定を指示したというふうな報道がございました。現場で働く皆様の声を反映し、全産業並みに、あるいはそれ以上の賃上げで人手を確保するプランにするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○福岡国務大臣 御指摘の医療、介護、障害福祉分野における生産性向上につきましては、これは、車座で関係者の方々から御意見を聞く、その場におきまして、総理から、将来に向けた生産性向上のための省力化投資促進プランを策定するように直接御指示をいただいたところでございまして、今、その方策の具体化に向けて検討を進めさせていただいているところでございます。
足下の賃上げに向けた対応としましては、令和六年度報酬改定において講じた賃上げに係る措置と、補正予算において盛り込んだ更なる賃上げや生産性向上の支援が現場に確実に届くよう、引き続き、現場の状況を適切に把握しながら、賃上げや生産性向上が進むように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○本村分科員 是非、人も増える、そして賃金も全産業並みに少なくとも上がっていくということで、現場に光が見えるようにしていただきたい、そういうプランにしていただきたいということを強く求めておきたいというふうに思います。
今、介護の分野に移りますけれども、訪問介護が受けられない方々が出ております。高齢者の在宅介護を支える訪問介護事業所が各地で次々と休止や廃止に追い込まれております。昨年四月に政府が訪問介護の基本報酬を二から三%削減したことが、事業所が運営が難しくなってしまっている。
訪問介護事業所がない自治体は、昨年十二月末の時点で全国百七町村となり、僅か半年で十町村増えました。長野県の高山村というところでは、
昨年夏まで二つあった事業所が、ドミノ倒しのようにゼロになってしまった。村の社会福祉協議会が昨年九月末に休止をし、昨年十月に、民間の訪問介護事業所も突然その日に休止と村の方に県から連絡があったそうです。
昨年四月の基本報酬の引下げで、減収を補おうということで訪問回数を増やしたそうですけれども、それで職員の方々は疲弊をしてしまった、それで休止になってしまったということになっております。
私の地元でも、訪問介護事業所が休止になって、その利用されていた方を別の事業所に頼んだそうですけれども、ヘルパーさんがいなくて受け入れることができないというお声を、名古屋の事例ですけれども、お伺いをいたしました。また、私の地元の豊田市でも、訪問介護が受けられない方々がいらっしゃるということを病院からお伺いをしております。
石破総理は、近隣市町村でカバーしているというような御答弁もあったのですけれども、カバーできていない、介護が必要な方々がいらっしゃるという御認識は、大臣はありますでしょうか。
○福岡国務大臣 まず、この訪問介護につきましては、御承知のとおり、これまでも国会で様々な御議論をいただいてきたところでございます。長引く人手不足、物価高騰で厳しい状況にございまして、これは訪問介護も同様であるというふうに認識をしています。
地域における訪問介護の提供状況につきましては、厚生労働省の介護サービス情報公表システムのオープンデータによりますと、訪問介護事業所のない自治体は全国に約百町村程度存在いたしますが、訪問介護は広域利用のサービスでございまして、こうした自治体の大半では、近隣市町村の事業所等によるサービスを御利用いただいております。
また、個々の訪問介護事業所の運営状況につきましては、事業者の休廃止は対前年同月比でおおむね一割弱の増加となっている一方で、新規開業や再開も同程度ございまして、事業所の総数としてはやや増加している状況にございますが、廃止の主たる要因は人手不足となっておりまして、人材確保に大きな課題を抱えているものというふうに認識をしています。
こうした実態を踏まえまして、今回の補正予算等を活用し、地域の特性等を踏まえたきめ細かい対策を講じてございます。
要介護者の在宅での生活を支える柱の一つであります訪問介護につきまして、その運営が安定的に行われることは非常に重要であるというふうに考えておりまして、サービス提供や運用状況について、引き続き丁寧に把握してまいりたいと思います。
○本村分科員 まずは、訪問介護の基本方針の引下げを撤回していただき、介護報酬全体の大幅な引上げを図る再改定を至急行っていただきたいというふうに思います。
また、その際には、サービスの利用に支障が生じないよう、利用者の方々の負担、これは軽減を図る、そういう対策を是非講じていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○福岡国務大臣 先ほどおっしゃいました、大変今厳しい状況にある。そして、当然、令和六年の報酬改定で見込んでいた引上げ額では十分ではないという御指摘については、そういったことも踏まえまして、令和六年の補正予算において、また更なる処遇改善のための予算を措置させていただいたところでございます。
あわせて、そういった補正予算の額がこれから支給されていきますから、そういったものを踏まえた経営実態をしっかり把握した上で適切な対応を取ってまいりたいと考えています。
○本村分科員 現場に光が見えるように、医療や介護や障害福祉を支えてくださっている皆さんに希望が見えるように、是非、大幅な賃上げ、そのための財源の担保、確保を求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。