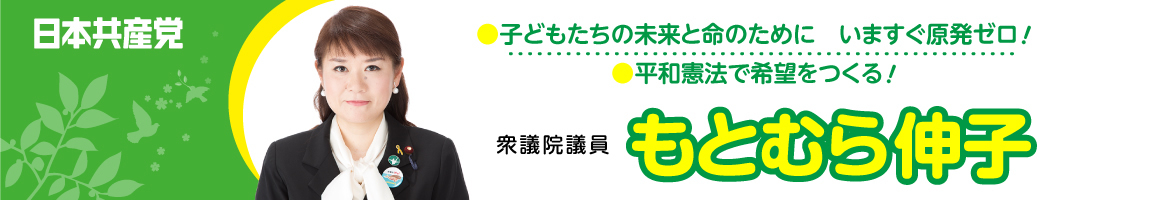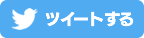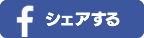広島県で衆議院予算委員会地方公聴会がありました。
長崎の被爆2世として、核兵器の廃絶に関することを質問しました。
また、マツダという大手自動車メーカーがある街ということで、下請け企業・取引企業で働く皆様はじめすべての労働者の大幅賃上げに関し、質問しました。
さらには、医療や介護で働く方々の人手確保と賃上げについて質問しました。
以下は、書き起こしです。長いですが、ご高覧いただければ幸いです。
=================
議事録
【核抑止論への反論、核兵器禁止条約、オブザーバー参加】
今日は、お忙しい時間を割いていただきまして貴重な御意見を聞かせていただいた四人の皆様に、心からの感謝を申し上げたいというふうに思います。日本共産党、衆議院議員、本村伸子です。
私は長崎の被爆二世でありまして、今日は広島に訪問させていただいたということで、まず原爆の問題、核兵器の廃絶の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。
今年は、被爆八十年という節目の年です。私はこの年を本当に大切な年にしていきたいというふうに思っております。広島や長崎の被爆者の皆さんが、本当に人生を懸けて魂の声を上げ続けてこられました。そのことが世界の人々の心を動かし、そして、都市としてもこの広島の皆さんが本当に大きな声を上げていただく中で、核兵器禁止条約、こういうところに実を結んだというふうに思っております。本当に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
まず、湯﨑知事にお伺いをしたいんですけれども、私、毎年、広島市の死没者慰霊式、平和記念式典、知事の発言を大変注目をしております。核抑止論者に対してしっかりと反論をされている、
このことに私は大変敬意を申し上げたいというふうに思っております。
湯﨑知事に是非核兵器廃絶への原点と核抑止論についてのお考えを改めてお伺いをしたいというふうに思います。また、被爆八十年に際して思うところを是非お聞かせいただけたらというふうに思っております。
ありがとうございます。
原点といいますか、やはりここは被爆地でありますので、被爆地広島市、そしてその広島市を抱える広島県の首長としてこの核兵器の問題にしっかりと取り組むということは、我々に課せられた一つの宿命というか使命というか、そういうものだというふうに私は認識をして取り組んでいるところでございます。
核抑止論については、いろいろなところで私も発言させていただいていますけれども、非常に重要だと思っていますのは、核兵器というのは物理的な現実として存在をしているわけですね。核抑止論というのはいわばゲーム理論でありまして、ゲーム理論というのは、人間のサイコロジーに依拠した頭の中の存在、戦略であるとかそういったものであります。
頭の中で考えていることというのは物理的な現実には勝てないというふうに思っておりまして、物理的に核兵器が存在する限り、これが使われる可能性というのは絶対になくならない、どんなに抑止という考え方をもってしても使われる可能性がある。これは、過去の人類の歴史の中でいわゆるリアリズムと言われるような抑止の考え方がありますけれども、破られたことがないことは一度もないというふうに思っています。
そういう意味で、核兵器はいろいろな理由で今のところ使われていないということもありますけれども、これが永遠に続くというふうにはとても考えられない。それが使われたときには残念ながら人類も地球も存続不可能になってしまうおそれがあるということを考えると、やはり物理的な現実を早く排除をしていくということが重要だというふうに考えているところでございます。
これについては、広島県は、僅かながらの我々の乏しい資源を使って、核抑止論、核兵器がない世界はどういう安全保障になるのかということですね、核抑止を代替する安全保障論ということを考えていかなければその次の世界というのはできないということで、そういった研究も海外のトップの研究機関と連携しながら進めているんですけれども、実は私は、是非日本政府にもこういった研究に資源を投下していただきたいなというふうに思っておるところでございます。
ありがとうございます。本当に重要な発言を毎年していただいていることに心から敬意を申し上げたいというふうに思います。
私の地元は愛知県なんですけれども、愛知にも広島の被爆者の方々がいらっしゃいます。被爆者の方々から、広島の被爆者の方から、ノーベル平和賞の授賞式にも参加をされた方なんですけれども、自分が生きているうちに、被爆者が生きているうちに核兵器禁止条約に批准をしてほしいという、本当に切なる思いを伝えていただいております。そして、少なくともオブザーバーとして締約国会議に参加をしてほしいという思いを私もいつも聞かせていただいて、本当に被爆者の皆さんの思いに応えていかなければいけないというふうに痛感をしております。
先ほど四人の皆様から、それぞれこのオブザーバー参加や核兵器禁止条約に関するお言葉をいただきましたので、私からは繰り返し質問はしないわけですけれども、是非政府にも、そういうふうに、私たちも党としてもしっかりと今も伝えておりますけれども、与野党を超えて、この点では力を合わせていきたいというふうに思っております。
もう一つなんですけれども、広島の原爆投下後の黒い雨の裁判で勝利をしたわけですけれども、日本政府の新たな線引きの下で、約300人の方が被爆者として認定をされずに却下をされているという現実をお伺いをいたしました。
国の責任で証言に基づく再調査を行い、黒い雨の降雨の地域を今きちんと確定をしていくことが必要だというふうに考えております。やはり、被爆者の方々は高齢化をして、証言できる方がいなくなってしまう。私の父も体が弱っておりまして、本当に被爆者の方々がいなくなってしまう、そういう時代が来てしまうのではないかということを大変心配をしておるんですけれども、やはり、今やらなければ永久に不明になってしまうというふうに思います。
被爆の実相、この黒い雨の降雨域もそうなんですけれども、被爆の実相を更に鮮明に明らかにしていくというために、今国がやるべきことという
ことを四人の方にお伺いできればというふうに思っております。
ありがとうございます。
黒い雨については、今般、菅総理の大きな決断によりまして降雨域の拡大というのはされました。それは、その他の地域に降っていないということを確定したわけではありませんので、やはり一定の線を引かないと、事務処理をするという意味では非常に大変になる、一つ一つ全部検証するというのは大変なので、それを簡易化するという意味ではよかったと思いますし、残りのところについては、今度は逆に少数になっていますので、きちんと検証しながら認定をいただければと思います。
その他、被爆の実相というのはますます今後伝えていくのが難しいというふうに思いますので、今広島市が様々な、AIなんかも使いながら、この伝承の努力をしております。そういったことを、やはり、ラストミニットといいますか、強力に進めていく必要があろうかというふうに思っております。
被爆の実相を伝えるということに対して意見したいと思いますけれども、先ほどおっしゃられたとおり、広島県の被団協の方から言われる言葉が、私たちが生きているタイミングで核兵器廃絶というのは難しいかもしれないけれども、命ある限り闘うという、私もこれで感銘を受けているんですけれども、それをちゃんと次世代に引き継ぐというのが我々の役目だと思っています。これも、連合もその役割を担っていると思います。
そうした意味で、年々この被爆の実相というのが、そうした八十年前にあったことが薄れてきているというのは間違いない、そのスピードを緩めること、確実につなげていくというのが我々の役目であるので、連合としても、若者を集めた、今できる、被爆者から話を聞かせてあげるということ、その人たちから伝わるようにしていくというのが我々の役目だと思いますので、連合としては、そういう取組を更に強化していきたいと思います。
ありがとうございます。
連合会としての考えじゃないんですけれども、被爆された方が高齢化する中で、時間がなくなってきておるという具合に思いますので、実態も把握した上で適切な措置ができればいいなという具合に思っております。
以上です。
被爆者の人が高齢化をし、どんどん亡くなっていく中で、この実相をどう伝えていくかというのは大変大きなテーマであり、これをいかに次世代につないでいくか、そのために、若者たちにこの実相をどのような形で伝えていくのかというのは、大変重要なのではないかというふうに思います。
もちろん今ある被爆者の方々の声をアーカイブすることも重要でありますけれども、生の声としてどういうふうに発信していくかというのは大変重要で、そういう取組を我が市においても少しずつやっていく必要があるのではないかというふうに考えているところです。
【すべての労働者の大幅賃上げ 自動車産業、ケア労働】
それぞれ貴重な御意見をこの点に関しても言っていただいて、ありがとうございます。
続きまして、賃金の引上げについてお伺いをしたいというふうに思っております。
私は愛知県の豊田市出身なんですけれども、マツダさんとトヨタ自動車さんと少し比較をしてみましたけれども、下請の方々に、価格転嫁の問題でいいますと、今、中小企業庁の方が調査をしておりまして、各企業さんがどういう状況なのかということを調べております。
そうしますと、マツダさんでいいますと、価格転嫁、しっかりとコスト増の分、原材料費の高騰、エネルギー価格の高騰、労務費の高騰分のところの価格をどのくらい補償しているかというと、一番上の方の七割以上というところに位置をしておりまして、残念ながらトヨタ自動車さんは四割台から六割台のところのグループにいるんですけれども、自動車・自動車部品の下請中小・小規模事業者の皆さんでいうと51・9%しか、コスト増した分の51・9%しか補償されていないという現実がありまして、やはり最上位の企業が100%補償するということをしっかりとルールづけなければ、なかなか。国の方も、少しずつではありますけれども、改善しているんですが、それをずっと続けていくと多分何年もかかってしまう、十年単位でかかってしまうという状況で、やはり今すぐ上げなければいけないというふうに思っております。
そういう下で、私も総理に質問させていただいたんですけれども、その後に、企業取引研究会というものをやって、それで下請法の改正というふうになってまいりました。ここで下請さん、取引企業さんと上位の企業と協議をすることを義務づけるというふうになってまいりましたけれども、協議をしても100%補償しなくてもいいみたいにも取られかねないんですけれども、ルールを作るという観点についてはどういうお考えをお持ちかということを、是非大野会長にお伺いをしたいというふうに思っております。
ルール作り、大切だと思います。それが、パートナーシップ構築宣言、宣言をするということだと思います。その宣言に基づいて、全ての発注元になる、発注になる、請負になる企業がそれに沿ってやるということです。
これまで、恐らく、長い歴史の中で、二次、三次会社になればなるほど、請負になると言い値でやっているというところもあるやに聞いております。それが、今回のこの宣言をする、この様式に沿って取り組むということが大切であって、いつまでも値上がりをする、原材料価格が上がるということじゃないので、では下がったときにはどうするかということも含めてこの宣言の下で取り組むというのが必要でありますので、是非、このパートナーシップ構築宣言に基づいた対応が全ての企業でできるように改めてお願いしておきたいと思います。
ありがとうございます。
私からすると、100%補償しないというのは不公正な取引であるというふうに感じてしまうんですけれども、アメリカでは、不公正な取引に対して三倍の賠償請求ができるというルールがあるということで、そういった厳しめのルールも必要なのではないかというふうに思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。大野会長、できればお願いをしたいと思います。
難しい質問ですね。そこまでしなくてもいいように、平和な日本であってほしいと思います。
ありがとうございます。
続きまして、医療や介護の労働者の確保というのは、本当に、社会の維持にとって、そしてこれから経済成長をしていく上でも、非常に大事な基盤だというふうに思っております。しかも、切迫した課題だというふうに思っております。
私の地元は愛知県の豊田市ですけれども、合併した旧町村の部分で、訪問介護ができない、ヘルパーさんが派遣できない地域が実際に出てきておりまして、介護が必要にもかかわらず訪問介護が受けられないという現実が実際にあるということを地域の病院からお伺いをしております。
愛知県の第二番目の都市でもそうであるのであれば、全国どこでもそうであるのではないかというふうに思うんですけれども、この広い広島県内でそういう状況がないのかという点をお伺いしたいのと、賃上げにおきましては、医療や介護の分野といいますと、本当に置き去りにされている現状がありまして、その点での問題意識、国への要望を是非聞かせていただきたいなというふうに思っております。これは、湯﨑知事、大野会長、髙垣市長にお願いを申し上げたいと思います。
まず、訪問介護の状況ですけれども、御指摘のように、非常に厳しい状況にあるというふうに理解をしております。これは、介護者もそうですし、ケアマネについてもそういう状況がある。どの程度まで実際に介護ができていない人たちがいるかというところまではまだ把握できておりませんけれども、我々、業界の皆様からお話を聞くと、非常に厳しい状況であるということは伺っております。
この介護、看護の処遇改善というのも非常に重要だと思いますけれども、これは公的価格に基づいたものになっておりますので、今これは、来年我々はまた取り組む予定にしておりますけれども、やはり、生産性の向上というか、新しいテクノロジーも導入をしていくということと、それからもう一つ、算定の部分でいいますと、やはり、特に中山間地域においては、移動の時間が非常に時間がかかるんですけれども、それが考慮されないというところでの苦しさということがあるので、そういったことについては、是非制度的な改善を図っていただきたいと思います。
一方で、ただ、それがどんどんどんどん上がると、今度は介護保険がすごく高くなってしまうという問題もあるので、そこでもう一度戻って、先ほどの生産性向上といったことも非常に重要な取組ではないかというふうに思っております。
訪問介護、その現状というのはちょっと認識していないんですが、いろいろな意見を聞くのは、やはり、実態、足りていないという話と、訪問介護だけじゃなくて、既にこういう経営がもう成り立たなくなっているんじゃないかな
というふうに思います。現実的に破綻をする、そういうのも、この広島県下でも起きているような気がしています。
その理由は、やはり元々収益が上がる仕組みじゃないということで、今、周りが賃金が上がっている中で、極端に賃金の差が開いてしまった、決して高くない、むしろ低過ぎるという賃金だと思っています。
そういったところに対して、やはり国としてもっと分厚い支援をすべきじゃないかなというふうに思っていますので、そのことをお伝えして意見とします。
中山間地域も多く抱える我が市にとっても、この医療、介護人材の確保というのは大変大きな問題です。今、その確保で非常に困難であるという状況にはないところでありますけれども、いずれ、近い将来、そういうことにもなり得るというようなことを考えています。
医療については、恐らく遠隔医療の議論が国においてもされていると思いますけれども、そういうところで一定のカバーはされるかも分かりません。しかし、介護においては、これはなかなか、マンパワーをどう確保するかということが課題になりますし、それについては、恐らく処遇改善をどういうふうにしていくのかということも、これは大変重要だと思いますし、あるいは、介護人材とともに新しいテクノロジーで、例えばロボットみたいな話であるとか、そういうふうなこともやりながらカバーをしていくような時代がもうまさに目の前に来ているのではないかという認識を持っているところです。
大変厳しい状況下に現在なりつつあるという認識をしているところです。
貴重な御意見、本当にありがとうございました。